
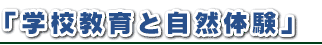

- 第6回 - 著者 星野 敏男
自然把握能力を育む
自然認識力というのは、ちょっと個々に分析分類するのがむずかしいような、文化的基盤を持った、自然把握能力だと思っています。自然を全体としてとらえる能力、全体把握能力、とでもいったら良いのかもしれません。とにかく、狭い意味でのエコロジー的な視点よりももっと広く、そこに生活する人々の日々の営みや暮らし、考え方なども含めて、一緒くたに、把握する能力だと思います。
少し解説しますと、こどもたちは、成長の過程でさまざまなものの見方、考え方を身につけ、それが一つの概念となって、身についていきます。概念の発達については、あるモノや自然物に対して、そのモノの「見た目とか色や形、肌だざわり、におい」など五感で認識した、あれこれを総合して、まず、最初にモノとしての概念が、作られていくといわれています。
そうして出来上がったモノの概念(あるいは、名詞といっても良いでしょう)と、そのモノをとりまく、まわりとのつながりや関係の中から、時間と空間をともなうコト概念(いわゆる動詞)となり、さらにそれが(美しいとか大切なといった)抽象的な価値を伴う形容詞としてのコト概念へと、発展していくと言われています。
私が体験した例のヤマメ釣りでいえば、ヤマメという概念(名詞)を先に教えてもらったのではなく、釣りという行為や、体験を通しているうちに、さまざまな認識が総合されて次第にヤマメという概念が形成され、そのヤマメの生き様や、まわりとのつながりを考えるうちに、ヤマメが生きるとはどういうことか、というコト概念に発展し、やがてヤマメの持つその美しさや価値、ヤマメが棲息する地域や、そこでの人々の生活にまで、認識が広がっていくという、発展的段階を踏んでいったように思われます。
モノ概念には体験が重要
 モノ概念というのは、本来そのものが持つさまざまな属性が、本人によって実際に統合されて、はじめてモノとして認識されるはずですが、体験を経ずに、教科書だけを通して教えられる自然というのは、実体としてイメージできない、きわめて狭い範囲での、モノ概念として把握されていく恐れがあるのではないか、と常々心配しています。
モノ概念というのは、本来そのものが持つさまざまな属性が、本人によって実際に統合されて、はじめてモノとして認識されるはずですが、体験を経ずに、教科書だけを通して教えられる自然というのは、実体としてイメージできない、きわめて狭い範囲での、モノ概念として把握されていく恐れがあるのではないか、と常々心配しています。また、このような自然の把握の仕方は、当然そのモノが持つ性質や機能、すなわち関係性の中でそこで生きている、というコト概念として認識されていかないばかりか、当然のことながら、価値を含んだような認識にまで、イメージは発展していかないだろうと思われます。自然の中での体験が少ないことの危惧、子どものうちに自然の中で、あれこれ体験してみることの重要性は、まさにこの点にあると思います。
このシリーズの前の号で、「雪が溶けると何になる?」という問いに対して、「水になる」という科学的自然観と、「春になる」という感性的自然観の違いや、形式知でとらえる自然観や、暗黙知としてとらえる自然観の違いについて触れていますが、今回のシリーズでの自然についての見方、とらえ方は、これらとも深い関係を持っています。
また、養老孟子先生がいろんな著書で述べている、情報として自然を見る見方と、実体として自然を見る見方の違い、とも言えるのではないでしょうか。この違いの境目を、養老先生は「バカの壁」と呼んでいるようにも思えます。
認識の場を提供するのが大人の義務
私は、自然体験活動や、野外教育など体験を通した教育の本質は、この情報として自然を見る見方と、常に変化する実体として自然を見る見方、つまり科学的・教科書的な自然の見方と感性的・文化的な自然の見方双方の見方を壁を作らずに、バランス良くつなげる役目にあると思っています。また、この双方の自然の見方とらえ方は、将来を担う日本の子どもたちが、大人になるまでには、必ず身につけていかなければならない自然の見方と、とらえ方でもあり、子どもたちにそのような認識力が、身につく場を用意し提供することが、日本の大人達の義務でもあろうと思っています。
■バックナンバー
 なぜ、いまなぜ自然体験が必要なのか(1)
なぜ、いまなぜ自然体験が必要なのか(1) なぜ、いまなぜ自然体験が必要なのか(2)
なぜ、いまなぜ自然体験が必要なのか(2) なぜ、いまなぜ自然体験が必要なのか(3)
なぜ、いまなぜ自然体験が必要なのか(3) 学校教育と自然体験(1)
学校教育と自然体験(1) 学校教育と自然体験(2)
学校教育と自然体験(2) 学校教育と自然体験(3)
学校教育と自然体験(3) 学校教育と自然体験(4)
学校教育と自然体験(4) 学校教育と自然体験(5)
学校教育と自然体験(5) 学校教育と自然体験(6)
学校教育と自然体験(6)■著者紹介
星野 敏男(ほしの としお)
1951年栃木県生まれ。
明治大学 教授
東京教育大学卒業。筑波大学大学院で野外活動を研究。
野外教育全国会議実行委員長、日本野外教育学会理事、日本キャンプ協会理事などを務める。自然体験・野外教育の研究分野では日本の第一人者のひとりとして著名。
著書、論文多数。
■関連情報
 社団法人日本キャンプ協会
社団法人日本キャンプ協会