
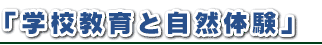

- 第5回 - 著者 星野 敏男
前回は、ある人には見えているのに、別な人には見えていないこととか、目には映っていると思われるはずなのに、見えていないといった、自然に対する人の認識力の違いについて触れました。
同じ場所に立っていれば、みんな同じものが見えているかというと、実は、自然の見え方というのは、人それぞれに違った見え方をしていて、自然界の何に対して意味を見いだすか、あるいは何に対して価値を見いだすかによって、当然自然の見え方も異なってくるようです。地元の方と一緒に山菜採りや、きのこ狩りなどを体験したことのある方も、このことはよくわかると思います。
アフォーダンス
ある人にとって見えていないものというのは、実は最初から、その人の目にも映っていないのではないでしょうか。つまり、自然の中から、みんなに同じ情報が入っていて、その情報の解釈の仕方が、個人によって異なって、結果として違ったアウトプットになるというのではなく、もともと自然の中から引きだす情報そのものが、個人によって異なっていたり、あるいは、そこにある情報が情報そのものとしてとらえられていない、ということだろうと思います。
ものの見方や、とらえ方に対するこのような考え方は、アフォーダンスとも呼ばれています。常に変化し続けるプロセスとしての環境や自然の中から、固定した情報として何を切り取るか、何をピックアップするかで、環境に対する人の振る舞いや行動は異なってきます。
子どもの頃から培うことが大切
 自然の中に子どもたちを連れ出しても、皆一様に同じ感覚で自然を見ているかというと、そうでもありません。こどもたちは自然や体験の中から、その子独自の方法で感じるものが、たくさんあります。自然の側が備えている、自然が持っている情報を、たくさん感じ取れるようになるためには、やはり、子どもの頃から直接自然に触れ、体験し、多くの情報を読みとったり、感じ取れる能力を培っておく必要があるでしょう。
自然の中に子どもたちを連れ出しても、皆一様に同じ感覚で自然を見ているかというと、そうでもありません。こどもたちは自然や体験の中から、その子独自の方法で感じるものが、たくさんあります。自然の側が備えている、自然が持っている情報を、たくさん感じ取れるようになるためには、やはり、子どもの頃から直接自然に触れ、体験し、多くの情報を読みとったり、感じ取れる能力を培っておく必要があるでしょう。ただし、学校教育での自然教育・環境教育は、注意しないと逆に「一方的な、あるいは狭い偏った自然の見方」や、「教科書的な見方」だけを児童生徒に植え付けてしまう恐れがあることにも、充分注意する必要があるでしょう。
体験を通さずに「頭だけで」あるいは「教科書だけで」自然について知っているというのは、隔靴掻痒というか、アユの釣り方は知っているのに、肝心の野アユのいないポイントで釣りをするような、なんともちぐはぐな感じもします。
きっかけづくりと良質な指導者
もちろん、自然認識の形成については、野外で何かをすればそれで簡単に自然認識が形成されるかというと、事はそう簡単ではないと思います。野球を見たこともない、やったこともない人に、いきなり野球をさせたり見せたりして、「ね、面白いでしょう!」といっても、そう簡単に面白さが伝わりませんし、また、そのひとが自分から野球をやってみようと思わないのと同じように、「自然っていいでしょう、面白いでしょう」と言っても、すぐには行動化につながらないことの方が多いと思います。自然認識を形成してもらうためには、野球放送に解説者がいるように、やはり、じょうずな解説や指導者の存在と、きっかけづくりが必要かと思います。
インタープリターが必要
目に見える極端な面白い活動や、冒険的なプログラムなどを提供するのであれば、活動自体が面白いですから、子どもたちもすぐに飛びつくでしょう。しかし、たとえば、活動を通して環境意識や、自然認識といったものを形成していくことを目標に置く場合は、それなりの仕掛けが必要だと思います。特に、いわゆる里山や田舎を前にしただけでは、その良さだったり、大切さは、子どもばかりか大人も、簡単に気づかないと思います。その良さ、あるいは、その地域の文化などを、実感を通してわからせてくれる仲立ち(インタープリター)が必要ですし、それを促すような有効なプログラムも、必要になってくるでしょう。
科学的なものの見方や、科学的な自然観の育成については、主に学校の教室の中で教科書を通して教えられます。
では、感性的な自然観とか、自然認識力や日本の文化的な自然の見方や地域文化は、だれが、いつ、どこで、子どもたちに身につけさせていけば良いのでしょうか。日本の文化にとって、これはきわめて重要な課題ではないかと思います。
■バックナンバー
 なぜ、いまなぜ自然体験が必要なのか(1)
なぜ、いまなぜ自然体験が必要なのか(1) なぜ、いまなぜ自然体験が必要なのか(2)
なぜ、いまなぜ自然体験が必要なのか(2) なぜ、いまなぜ自然体験が必要なのか(3)
なぜ、いまなぜ自然体験が必要なのか(3) 学校教育と自然体験(1)
学校教育と自然体験(1) 学校教育と自然体験(2)
学校教育と自然体験(2) 学校教育と自然体験(3)
学校教育と自然体験(3) 学校教育と自然体験(4)
学校教育と自然体験(4) 学校教育と自然体験(5)
学校教育と自然体験(5) 学校教育と自然体験(6)
学校教育と自然体験(6)■著者紹介
星野 敏男(ほしの としお)
1951年栃木県生まれ。
明治大学 教授
東京教育大学卒業。筑波大学大学院で野外活動を研究。
野外教育全国会議実行委員長、日本野外教育学会理事、日本キャンプ協会理事などを務める。自然体験・野外教育の研究分野では日本の第一人者のひとりとして著名。
著書、論文多数。
■関連情報
 社団法人日本キャンプ協会
社団法人日本キャンプ協会