
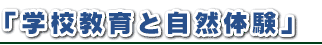

- 第3回 - 著者 星野 敏男
今回は、自然認識、特に感性的な自然認識や科学的な自然認識について触れてみます。まず、個人的な体験談から紹介しましょう。
清流が毎日の遊び場
 私が生まれ育ったところは、栃木県鹿沼市の草久(くさきゅう)というところですが、地元では西大芦と呼ばれている山間地域で、日光と足尾の峠あたりを源流とする大芦川という清流沿いに集落が点在しています。家のすぐ目の前の清流が毎日の遊び場で、典型的な川ガキでした。そのような地域で生まれ育ったため、幼稚園のころ、といっても幼稚園はありませんでしたが、その頃には、すでに毎日のように一人前に釣りもしていました。
私が生まれ育ったところは、栃木県鹿沼市の草久(くさきゅう)というところですが、地元では西大芦と呼ばれている山間地域で、日光と足尾の峠あたりを源流とする大芦川という清流沿いに集落が点在しています。家のすぐ目の前の清流が毎日の遊び場で、典型的な川ガキでした。そのような地域で生まれ育ったため、幼稚園のころ、といっても幼稚園はありませんでしたが、その頃には、すでに毎日のように一人前に釣りもしていました。見よう見まねでヤマメを釣った
川で釣れる魚は、最初の頃はザッコと呼ばれるハヤがメインでしたが、小学3年生くらいになると、やも(ヤマメの地元の呼び名)という魚もたまに釣ることができるようになってきます。ヤマメという魚は、流れてくる水棲昆虫や川面をながれてくる、小さな羽虫や昆虫などを素早く捕捉する魚で、子どもにはなかなか釣るのがむずかしい魚なのですが、あれこれ工夫したり、大人の見よう見まねでなんとか釣れるようになっていきます。
不思議な体験
そんなある日のことです。確か、小学校4年生の頃だったと思いますが、釣りの最中に不思議な体験をしました。それはまるで悟りを開いたような、一気に世の中が明るくなるような体験で、一瞬にして水底から水中、空、山までがすべてつながって見えてきたのです。
それまで、親父や大人の人たちの釣り方を見ていて、ヤマメの釣れそうなポイントや、ヤマメがいつもいそうな場所というのは、ある程度わかっていたのですが、それでも、その日までは、ただひたすら、私と釣り竿と糸とエサと魚という関係で、釣りを見ていたのです。
川の中を考える、という視点の変換ができた
ところが、その日は、なんとなく、「ヤマメは流れてくる川虫や、水面を流れてくる虫を食って生きてるんだよなぁ~」とか「川虫は上流から流れてくるんだよなぁ~」とか考えて、そのときふと、「そうか、魚はいちばんエサを捕りやすいところに陣取ろうとしてるんだ」「たくさんエサが流れて来る場所には、いちばん力のある大きいやつが陣取るんだ」といったことから、「小さいうちから空からはヤマセミやカワセミ、また水中でも、より大きな魚などに、いつもねらわれているから、とっさに隠れる場所が、近くにあるところが好きなんだな?」とかいつのまにか、水中のヤマメの視点から、川の中を考えるという視点の変換を、無意識のうちにやっていたようです。
そうしたら、川虫という水棲昆虫から、それを食べる魚、その魚を襲うより大きな魚や空からの鳥の攻撃など、あれやこれやが一瞬にしておおきなつながり、まとまりとして体の中に入ってきたのでした。今思えば、単純なことだったのですが、その時は本当に世紀の大発見をしたような気分でした。
自然観は子ども時代の体験から
その日の体験は、いわゆる食物連鎖に近いような見方で、川や魚を見た初めての体験だったように思うのですが、しかし、よくよく考えてみると、後に教科書で教わるような食物連鎖的な見方とは、ちょっと違った体験でした。つまり、平面的連鎖といったらいいのか、図に表される生き物だけの連鎖といったらいいのか、そういうものとは、ちょっと違った感じで、その地域で暮らしているひとびとだったり、季節だったりを、すべてを含むような総体的なつながりを見ていたように思うのです。
感性的な自然認識とか、科学的な自然観などについて、あれこれ考えるたびに、この小学生の時のきわめて個人的な体験が、鮮やかによみがえってきます。・・・この話、続きます。
■バックナンバー
 なぜ、いまなぜ自然体験が必要なのか(1)
なぜ、いまなぜ自然体験が必要なのか(1) なぜ、いまなぜ自然体験が必要なのか(2)
なぜ、いまなぜ自然体験が必要なのか(2) なぜ、いまなぜ自然体験が必要なのか(3)
なぜ、いまなぜ自然体験が必要なのか(3) 学校教育と自然体験(1)
学校教育と自然体験(1) 学校教育と自然体験(2)
学校教育と自然体験(2) 学校教育と自然体験(3)
学校教育と自然体験(3) 学校教育と自然体験(4)
学校教育と自然体験(4) 学校教育と自然体験(5)
学校教育と自然体験(5) 学校教育と自然体験(6)
学校教育と自然体験(6)■著者紹介
星野 敏男(ほしの としお)
1951年栃木県生まれ。
明治大学 教授
東京教育大学卒業。筑波大学大学院で野外活動を研究。
野外教育全国会議実行委員長、日本野外教育学会理事、日本キャンプ協会理事などを務める。自然体験・野外教育の研究分野では日本の第一人者のひとりとして著名。
著書、論文多数。
■関連情報
 社団法人日本キャンプ協会
社団法人日本キャンプ協会