
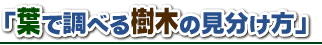

~ 春編3「カエデ」 ~ 著者 林 将之
■切れ込みの入る葉・・・カエデの仲間を見分けよう
芽吹いたばかりだった小さな葉もだんだんと開き始め、だいぶその形が分かるようになってきました。中でもカエデのように切れ込みの入る葉は、芽吹きの頃からその形が分かるので、早い段階から他の樹木と区別することができます。今回はこのようなカエデの仲間の見分け方を中心にお話しします。
切れ込みの入る葉のことを、分裂葉(ぶんれつよう)と呼びます。いわゆる「もみじ」や「かえで」と呼ばれる葉の形を思い描いていただければ間違いありませんが、そのような典型的な形以外にも、1~2カ所しか切れ込みが入らない形もあれば、10カ所以上の切れ込みが入る形もあります。また切れ込みの深さも様々で、付け根近くまで切れ込みむ形もあれば、ごく浅くしか切れ込まない形もあります。
■まず、カエデの仲間か否かを見分ける
|
分裂葉を持つ樹木で最も多く見られるのは、やはりカエデ科の樹木です。一言に「カエデ科」と言っても、日本にはざっと20~30種が分布しており、その種類を正確に見分けるとなるとずいぶんと敷居が高く感じられてしまいます。そこでまず、カエデ科なのか、そうではないのか、を見分けることから始めましょう。 カエデ科の樹木には大きな特徴があります。それは、葉が対生(たいせい:枝に2枚が対になってつく)するということです。高さ3m以上の木で、分裂葉を持ち、葉が対生であれば、カエデ科と思ってほぼ間違いありません(カンボク、キリなど一部例外もあります)。 |
 イロハモミジの葉。 |
このように、葉の形が似ていても対生か互生かで決定的に種類が異なるので、葉のつき方を見ることには大きな意味があります。
■角の数を数えてみよう
カエデ科であることが分かったら、次はその葉がいくつに分裂するかを数えてみましょう。数え方は簡単、葉の角の数を数えれば良いのです。最も有名なイロハモミジの場合は、ふつう5または7個の角がありますが、幹が緑色で知られるウリハダカエデは3または5個ですし、ブナ林に多いハウチワカエデは9または11個の角があります。
このように分類していくと、角の数によってカエデ科の樹木を何グループかに分けることができます。また、その数は奇数が基本になっていることにも気づくでしょう。奇数ということは、軸となる“真ん中の角”が存在するということです。しかし生き物に例外はつきもの。1本の木の中でも、角の数が偶数の葉もときどき見られます。小さな角をどこまで数えるかによっても差が出ますが、四つ葉のクローバーと同じで“珍しい葉”を探す楽しみにもできます。(四つ葉のクローバーよりはずっと簡単に見つかると思いますが。)
カエデ類を見分ける上でもう一つ知っておくと良いことは、その分布域です。カエデ科の樹木は、ブナ林などの寒い地方を中心に分布するので、北日本の場合を除くと、低地の雑木林などに見られる種類はかなり限られています。以下に、葉の角の数と分布域で主なカエデ科の樹木をグループ分けしてみました。ただし、角の数や分布域は一概に言えない場合もありますのでご注意ください。
| 標準的な角の数 | 低地でも見られる | 主に寒い地方で見られる | |
 |
・3(または1) |
●ウリカエデ ●トウカエデ(中国原産、植栽される) |
●カラコギカエデ |
 |
・3または5 ・葉は大きく幅広い ・切れ込みは浅い |
●ウリハダカエデ | ●ホソエカエデ ●テツカエデ |
 |
・5または7 | ●イロハモミジ |
●ヤマモミジ ●オオモミジ ●イタヤカエデ ●コミネカエデ ●アサノハカエデ |
 |
・9または11 | ●ハウチワカエデ ●コハウチワカエデ ●オオイタヤメイゲツ |
|
 |
・1(切れ込みなし) | ●チドリノキ ●ヒトツバカエデ |
このように分裂葉にはいろいろな形があり、その個体差が大きいのも特徴の一つです。カエデの仲間であっても、表のいちばん下に示したように切れ込みの入らない種類もあります。ヤマグワなどのクワ科の仲間では、若い木では切れ込みがある葉をつけるのに、木が大きくなると切れ込みのない葉ばかりになる種類もあります。個体差が大きいことを実感する上では、分裂葉を持つ木は良い例と言えるでしょう。
■バックナンバー
 葉で調べる樹木の見分け方 ~冬編1「基礎・冬芽」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~冬編1「基礎・冬芽」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~冬編2「冬の落葉樹」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~冬編2「冬の落葉樹」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~冬編3「常緑低木」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~冬編3「常緑低木」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~春編1「サクラ」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~春編1「サクラ」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~春編2「タラノキ」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~春編2「タラノキ」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~春編3「カエデ」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~春編3「カエデ」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~夏編1「ウルシ」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~夏編1「ウルシ」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~夏編2「ウツギ」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~夏編2「ウツギ」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~夏編3「掌状複葉」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~夏編3「掌状複葉」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~秋編1「どんぐり」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~秋編1「どんぐり」~■著者紹介
 林 将之(はやし まさゆき)
林 将之(はやし まさゆき)1976年山口県生まれ。編集デザイナー。
千葉大学園芸学部卒業後、植生調査や造園系雑誌編集の職歴を経てフリーに。2002年、学校法人中央工学校 非常勤講師。葉で樹木を見分けることをテーマに掲げ、樹木の観察指導やデジタル標本収集等に取り組んでいる。現在運営する樹木鑑定サイト「このきなんのき」では投稿写真から樹木の名前の鑑定を行っている。
著書「葉で見わける樹木」(小学館)
■関連情報
 樹木鑑定サイト「このきなんのき」
樹木鑑定サイト「このきなんのき」