
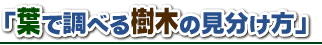

~ 冬編3「常緑低木」 ~ 著者 林 将之
■葉で常緑低木を見分ける
いよいよ葉だけで樹木を見分ける実践編に入りましょう。今回は、関東地方の雑木林内に生える常緑低木を見分ける例を紹介します。常緑樹は、冬でも葉をつけているので一年中葉で同定(名前を調べる)ができますし、低木はすぐ葉を手にとることができるので、最も手軽に調べられる部類です。
自然の森に生える樹木の名前を調べる場合は、まずその地域に分布している樹木の種類、つまり「植生」をある程度把握しておくことが近道です。日本には800種前後の樹木が生育していると言われますが、海岸近くの森、内陸の森、低地の森、山地の森などで、植生はいろいろ異なります。同じ低地の森でも、関東と関西ではかなり植生が異なることもあります。関東地方の低地の雑木林の場合、コナラ、クヌギ、イヌシデ、シラカシなどの高木の下に、アオキ、ヤツデ、モチノキ、ヒサカキなどの常緑低木が多く見られます。これに対し関西の常緑低木では、モチノキはあまり見られず、ソヨゴ、アセビ、シャシャンボなどがよく見られます。
今回はこれらの常緑低木の中でも、よく似た小型の葉をもつグループ(モチノキ、ヒサカキなど)を見分けてみましょう。
検索表を思い描く
葉で樹木を同定する場合は、本稿第1回で説明したように「葉の形」「対生か互生か」「鋸歯があるかないか」「常緑樹か落葉樹か」の4項目が基本となります。今回調べる樹木はすべて「常緑樹」で、葉の形もすべて裂け目のない「単葉」に絞ってみました。残りの2項目の違いによって、どのように分類できるかを示した検索表が下記です。
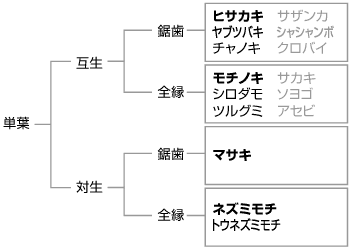

表中のグレー文字の樹木は、関東地方には自生が少なく、主に西日本で見られる樹木です。また、チャノキやトウネズミモチは日本産の樹木ではありませんが、野生化した個体が見られます。こうしてみると、4つのグループの違いを系統づけて把握することができます。特に対生の樹木は種類が少ないので、ネズミモチやマサキはすぐに見分けられる部類であるのに対し、モチノキやヒサカキのグループには類似種も多く、見分けるのが難しい部類と言えます。
 実際の葉を見て検索してみよう
実際の葉を見て検索してみようでは、この表を頭に入れたところで、実際の森の中に入ってみましょう。場所は神奈川県北部の海抜100mに満たない雑木林です。この森の中で、高さ2mぐらいの常緑低木に出会いました。枝先についた葉の写真(右)を見ながら、さっそく検索していきましょう。
まず葉の形は、最もありふれた形である「単葉」です。葉のつき方を見てみると、枝から葉が1枚ずつ互い違いに出ているので、これは「互生」です。そして、葉のふちにはギザギザの鋸歯があることが分かります。これで、上の4グループのどのグループか分類できたはずです。ヒサカキのグループですね。
決め手は細部のチェック
検索表を見てみると、ヒサカキと同じグループにはヤブツバキ、チャノキ、サザンカ、シャシャンボ、クロバイなどがあります。これらのどれかを見分けるには、葉の大きさや、葉柄(ようへい)の色や長さ、毛の有無など、細部をチェックしなければなりません。この際に、植生に関する予備知識があれば、後三者は関東平野には分布していないので除外することができます。
 まず葉の大きさを見ると、ヒサカキはだいだい4~5cmなのに対し、ヤブツバキはゆうに6~7cmあって丸い大きな葉なので、すぐに区別できます。チャノキは大きさは同程度ですが、葉の形がヒサカキより丸みを帯びた楕円形で、表面の葉脈が浮き出てよく目立つので、一度見比べれば違いが分かるようになると思います。またこの他にも、高木になる樹木、シラカシ、アラカシ、スダジイなどの幼木も林内に見られ、同様に互生で鋸歯があります。全縁のモチノキも、若い個体では鋸歯がある葉が出現することが多く、これとも見分けないといけません。
まず葉の大きさを見ると、ヒサカキはだいだい4~5cmなのに対し、ヤブツバキはゆうに6~7cmあって丸い大きな葉なので、すぐに区別できます。チャノキは大きさは同程度ですが、葉の形がヒサカキより丸みを帯びた楕円形で、表面の葉脈が浮き出てよく目立つので、一度見比べれば違いが分かるようになると思います。またこの他にも、高木になる樹木、シラカシ、アラカシ、スダジイなどの幼木も林内に見られ、同様に互生で鋸歯があります。全縁のモチノキも、若い個体では鋸歯がある葉が出現することが多く、これとも見分けないといけません。そこでヒサカキを見分ける上で大きなポイントとなるのが、葉先がわずかにくぼむという特徴です。これは同じツバキ科のチャノキやサザンカにも見られますが、その他の科の樹木にはあまり見られない珍しい特徴です。ちなみに、ヒサカキに対し「ホンサカキ」とも呼ばれるサカキは、鋸歯がないので別のグループです。関東平野ではサカキはほとんど生えないので、ヒサカキのことを単に「サカキ」と呼んでいることが多いようです。
論理的に捉えてこそ、正確な同定ができる
このような手順で、葉の形態で論理的に見分ける習慣をつけると、直感だけに頼らず、正確に樹木を見分けられるようになりますし、違う地域で違う樹木に出会ったときにも対応できるようになるはずです。
■バックナンバー
 葉で調べる樹木の見分け方 ~冬編1「基礎・冬芽」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~冬編1「基礎・冬芽」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~冬編2「冬の落葉樹」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~冬編2「冬の落葉樹」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~冬編3「常緑低木」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~冬編3「常緑低木」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~春編1「サクラ」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~春編1「サクラ」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~春編2「タラノキ」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~春編2「タラノキ」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~春編3「カエデ」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~春編3「カエデ」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~夏編1「ウルシ」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~夏編1「ウルシ」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~夏編2「ウツギ」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~夏編2「ウツギ」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~夏編3「掌状複葉」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~夏編3「掌状複葉」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~秋編1「どんぐり」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~秋編1「どんぐり」~■著者紹介
 林 将之(はやし まさゆき)
林 将之(はやし まさゆき)1976年山口県生まれ。編集デザイナー。
千葉大学園芸学部卒業後、植生調査や造園系雑誌編集の職歴を経てフリーに。2002年、学校法人中央工学校 非常勤講師。葉で樹木を見分けることをテーマに掲げ、樹木の観察指導やデジタル標本収集等に取り組んでいる。現在運営する樹木鑑定サイト「このきなんのき」では投稿写真から樹木の名前の鑑定を行っている。
著書「葉で見わける樹木」(小学館)
■関連情報
 樹木鑑定サイト「このきなんのき」
樹木鑑定サイト「このきなんのき」