
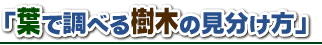

~ 冬編2「冬の落葉樹」 ~ 著者 林 将之
■冬の落葉樹の名前を調べる
森の冬は、落葉樹はすっかり葉を落として丸裸、鮮やかな花や実も少なく、否が応でも樹木に目が向かなくなってしまう季節です。そんな冬山でも、自然体験の活動を行っていると、落ち葉を拾って「これは何の葉?」、枝だけの木を見て「あれは何の木?」といった疑問は必ず出てくるものです。そこで今回は、冬の山道で出会った、一本の落葉樹の名前を調べる手順を紹介しましょう。
■1 あの木は何だろう?・・・まずは樹形
 ある寒い冬の日、関東のとある山道を歩いていると、道ばたに大きくて気になる木が現れたとしましょう。「あの木は何だろう?」。でも、葉はほとんどついていないし、花や実もありません。ただ空に向かって枝を広げているだけです。
ある寒い冬の日、関東のとある山道を歩いていると、道ばたに大きくて気になる木が現れたとしましょう。「あの木は何だろう?」。でも、葉はほとんどついていないし、花や実もありません。ただ空に向かって枝を広げているだけです。このように、 まずは樹形が自然に目に入ってくると思います。樹形だけで木の種類が分かればいいのですが、それはよほど特徴のある木でないと無理と言えます。ですから樹形を見るときは、中心に直立する幹(主幹:しゅかん)があるかないか、形は整形か不整形か、枝の出方や太さに特徴はないか、などといった点を意識して見てみましょう。
この木の場合は、主幹はあまりはっきりせず、形は不整形、枝はふつうと言えるでしょう。この時点で、まっすぐな主幹をもつトチノキやホオノキなどの可能性は低いと言えます。
■2 常に得られる情報・・・樹皮を見る
 さっそく近寄って、樹皮を見てみましょう。樹皮も、それだけでは木の種類を確定することはできませんが、一年を通して間近に見ることのできる貴重な情報です。この木の樹皮を見ると、縦に裂け目が入って、しま模様になっていることが分かります。
さっそく近寄って、樹皮を見てみましょう。樹皮も、それだけでは木の種類を確定することはできませんが、一年を通して間近に見ることのできる貴重な情報です。この木の樹皮を見ると、縦に裂け目が入って、しま模様になっていることが分かります。この時点で、横しま模様のサクラ類などは除外されますし、裂け目の入らないケヤキやエノキ、エゴノキなども違うようです。縦しま模様の樹皮をもつ木はたくさんありますが、関東の雑木林であることを考えると、コナラ、クヌギ、クリ、シデ類、ハリギリなどが有力と推測できます。同じ縦しま模様でも、その裂け方はさまざまなので、観察力と経験をもっていれば、樹皮でかなり種類を限定できる場合もあります。
 |
 |
 |
 |
|
コナラ
裂け目は中程度。白黒のしま模様になる。
|
クヌギ
白っぽくて、裂け目は深い。
|
クリ
黒っぽくて、裂け目は浅く少ない。
|
イヌシデ
しまは目立つが、凹凸はほとんどない。
|
■3 いちばんの手がかり・・・落ち葉を探そう
 大きな手がかりとなるのはやっぱり葉っぱです。森の中では、たくさんの落ち葉が入り交じっているので、どの葉がどの木のものかは特定しにくいですが、ある程度木の種類の見当をつけて探せば、ずっと探しやすくなります。
大きな手がかりとなるのはやっぱり葉っぱです。森の中では、たくさんの落ち葉が入り交じっているので、どの葉がどの木のものかは特定しにくいですが、ある程度木の種類の見当をつけて探せば、ずっと探しやすくなります。この木の足下を見渡してみると、コナラらしき落ち葉が多く見つかりました。コナラの葉は、葉先に近い方で葉幅が最大になる形で、縁のギザギザ(鋸歯)も鋭いので、比較的簡単に見分けられます。これに対し、クヌギやクリは細長い形、シデ類の落ち葉は小さく丸まってしまいますし、ハリギリはモミジ形です。しかし、コナラの葉は変異も大きいので要注意です。下の右端の葉もコナラですが、クヌギとの中間型を呈しています。葉っぱにも“個人差”が多く見られるのです。
 |
 |
 |
|
コナラ
|
クヌギ
|
コナラ(異形)
|
■4 小さいけど正確な情報・・・冬芽
 そして最後に、冬芽を確認することができたら、ほぼ確定と言えます。冬芽は、葉がつく枝につくので、大きな木では高すぎて手が届かないという問題もあります。その場合は、幹の根元近くから生える萌芽枝(ほうがし)と呼ばれる枝を探してみましょう。萌芽枝につく葉や芽は、他のそれと比べると若干形がいびつな場合もありますが、すぐ手に取れる貴重な情報源です。
そして最後に、冬芽を確認することができたら、ほぼ確定と言えます。冬芽は、葉がつく枝につくので、大きな木では高すぎて手が届かないという問題もあります。その場合は、幹の根元近くから生える萌芽枝(ほうがし)と呼ばれる枝を探してみましょう。萌芽枝につく葉や芽は、他のそれと比べると若干形がいびつな場合もありますが、すぐ手に取れる貴重な情報源です。コナラ類の冬芽は、芽を包む皮(芽鱗:がりん) の枚数が多く、枝先に数個がかたまってつくことが特徴です。コナラの芽は赤っぽく濃い色、クヌギは褐色で白い毛が生えています。この木の萌芽枝には、赤っぽい冬芽がついていたので、どうやらコナラで間違いないようです。
 |
 |
|
コナラ
|
クヌギ
|
■木の種類が分かったかな?
 いかがでしょうか? これが冬の落葉樹の名前を調べる手順の一例です。もちろん、専門家なら冬芽だけでも調べることもできますが、やはり情報量の少ない冬は、樹形、樹皮、落ち葉なども含めて、総合的に判断することが基本です。そのためには、消去法的に調べた方が分かりやすい場合もあり、幅広い知識が必要となるのも確かです。まずは、その地域に生えている樹木からよく把握することが近道です。木の種類をある程度特定できたら、周りにその木の実が落ちていないか探してみたり、春の芽吹きの時期に答え合わせをしにいく楽しみもできます。
いかがでしょうか? これが冬の落葉樹の名前を調べる手順の一例です。もちろん、専門家なら冬芽だけでも調べることもできますが、やはり情報量の少ない冬は、樹形、樹皮、落ち葉なども含めて、総合的に判断することが基本です。そのためには、消去法的に調べた方が分かりやすい場合もあり、幅広い知識が必要となるのも確かです。まずは、その地域に生えている樹木からよく把握することが近道です。木の種類をある程度特定できたら、周りにその木の実が落ちていないか探してみたり、春の芽吹きの時期に答え合わせをしにいく楽しみもできます。この木の根元の落ち葉をめくってみると、秋に落としたドングリが見つかりました。
■バックナンバー
 葉で調べる樹木の見分け方 ~冬編1「基礎・冬芽」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~冬編1「基礎・冬芽」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~冬編2「冬の落葉樹」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~冬編2「冬の落葉樹」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~冬編3「常緑低木」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~冬編3「常緑低木」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~春編1「サクラ」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~春編1「サクラ」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~春編2「タラノキ」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~春編2「タラノキ」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~春編3「カエデ」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~春編3「カエデ」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~夏編1「ウルシ」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~夏編1「ウルシ」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~夏編2「ウツギ」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~夏編2「ウツギ」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~夏編3「掌状複葉」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~夏編3「掌状複葉」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~秋編1「どんぐり」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~秋編1「どんぐり」~■著者紹介
 林 将之(はやし まさゆき)
林 将之(はやし まさゆき)1976年山口県生まれ。編集デザイナー。
千葉大学園芸学部卒業後、植生調査や造園系雑誌編集の職歴を経てフリーに。2002年、学校法人中央工学校 非常勤講師。葉で樹木を見分けることをテーマに掲げ、樹木の観察指導やデジタル標本収集等に取り組んでいる。現在運営する樹木鑑定サイト「このきなんのき」では投稿写真から樹木の名前の鑑定を行っている。
著書「葉で見わける樹木」(小学館)
■関連情報
 樹木鑑定サイト「このきなんのき」
樹木鑑定サイト「このきなんのき」