
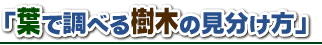

~ 冬編1「基礎・冬芽」 ~ 著者 林 将之
■木を見分けるのって難しい
樹木は、ひとたび外に出ればいくらでも生えていますが、いざ名前を調べようとなると、かなり難しいものです。他の生き物と比べると、虫や鳥、草花などは一目で全体が見渡せるのに対し、樹木は大きすぎて全体像がつかみにくく、幹や葉だけしか手に取れない、ということが多々あります。さらに、季節や老若で姿がかなり変わる上、生える環境などによってずいぶんと個体差があります。それ故、樹木の名前を見分けるにはどうしても経験値が必要になるのです。
■花・実・葉・冬芽で見分けられる
しかし、何でも経験や直感だけで見分けるわけにはいきません。動植物の名前を分類学的に調べることを「同定(どうてい)」と呼びます。樹木の同定方法には、花、実、葉、冬芽(ふゆめ)の主に4つの要素があります。この中で、アウトドア派のみなさんにまず覚えてほしいのは、葉で同定する方法です。一時期しか見られない花実や、詳細な専門知識が必要になる冬芽に比べると、いちばん身近で、いちばん実用的だからです。
■葉で検索する4つのポイント
葉で樹木を同定するには、まず4つの検索項目について調べ、候補種を絞っていくことから始まります。これらは、もっとも基本的かつ大事なポイントです。
1.葉の形
・標準形[単葉:たんよう]
・もみじ形[単葉(分裂葉:ぶんれつよう)]
・はね形[羽状複葉:うじょうふくよう]
・てのひら形[掌状複葉:しょうじょうふくよう]
・針葉樹
     |
・互い違いにつく[互生:ごせい]
・対になってつく[対生:たいせい]
  |
・ギザギザがある[鋸歯縁:きょしえん]
・ギザギザがない[全縁:ぜんえん]
  |
・常緑樹・・・色が濃く、つやがあり、厚くて硬い。
・落葉樹・・・色が薄く、つやは少なく、薄くて軟らかい。
  |
 |
■葉のない冬は冬芽が主役
冬は、常緑樹以外の樹木は葉を落としてしまうので、同定するのも大変難しくなります。そこで登場するのが、冬芽で同定する方法です。冬芽とは、枝先などについている小さな芽のことで、春に開く葉や花が格納されています。冬芽を見るときのポイントは、形、芽鱗(がりん:芽を包む皮)の有無や枚数、色、毛の有無などのほか、冬芽の近くにある葉痕(ようこん:葉のついていた痕)や、枝や幹の様子も同時に見ることが重要です。もちろん、落ち葉を探すことも大切です。
しかし、ほとんどの冬芽は1cm以下と小さく、形の違いも微妙であり、多くの情報から総合的に判断する必要があるので、やはり冬芽の同定方法は上級者向けといえるでしょう。ここでは、冬芽の中でも特に個性的で、覚えやすいものをいくつか紹介しましょう。
      |
●2番目はクリ(ブナ科)ですが、見ての通りクリの実に似た冬芽なので、これもユニークで分かりやすい特徴です。
●3番目はイロハモミジ(カエデ科)です。カエデ科の木は、葉が対生するのと同じで、冬芽も対生するので、ほかの種類と区別できます。
●4番目はコブシ(モクレン科)です。有名なネコヤナギ(ヤナギ科)の花とよく似て、ふさふさの毛に包まれています。この毛のある芽が花芽(かが)で、下の毛のない芽は葉芽(ようが)です。
●5番目はアカメガシワ(トウダイグサ科)です。 これは他の冬芽とは少し違って、芽を包む芽鱗がないので裸芽(らが)と呼ばれます。春に開く葉の赤ちゃんが、寒そうにちぢこまっています。
●6番目はキハダ(ミカン科)です。冬芽は小さいのですが、その周りを取り囲むU字形の葉痕が目立ちます。葉痕は葉がついていた痕なので、冬芽は葉の内側にくるまれていたことが分かります。
そのほか、葉痕が人や動物の顔に見える種類も多く、よく観察してみると新鮮な発見があります。このように、特徴のある冬芽から少しずつ覚えていくと、冬の樹木を見分けるポイントが少しずつ身についてくると思います。次回からは、葉の具体例とあわせて、実際に樹木を同定する手順を追ってみましょう。
■バックナンバー
 葉で調べる樹木の見分け方 ~冬編1「基礎・冬芽」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~冬編1「基礎・冬芽」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~冬編2「冬の落葉樹」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~冬編2「冬の落葉樹」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~冬編3「常緑低木」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~冬編3「常緑低木」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~春編1「サクラ」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~春編1「サクラ」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~春編2「タラノキ」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~春編2「タラノキ」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~春編3「カエデ」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~春編3「カエデ」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~夏編1「ウルシ」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~夏編1「ウルシ」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~夏編2「ウツギ」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~夏編2「ウツギ」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~夏編3「掌状複葉」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~夏編3「掌状複葉」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~秋編1「どんぐり」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~秋編1「どんぐり」~■著者紹介
 林 将之(はやし まさゆき)
林 将之(はやし まさゆき)1976年山口県生まれ。編集デザイナー。
千葉大学園芸学部卒業後、植生調査や造園系雑誌編集の職歴を経てフリーに。2002年、学校法人中央工学校 非常勤講師。葉で樹木を見分けることをテーマに掲げ、樹木の観察指導やデジタル標本収集等に取り組んでいる。現在運営する樹木鑑定サイト「このきなんのき」では投稿写真から樹木の名前の鑑定を行っている。
著書「葉で見わける樹木」(小学館)
■関連情報
 樹木鑑定サイト「このきなんのき」
樹木鑑定サイト「このきなんのき」