
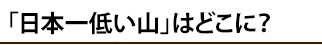

著者 節田 重節
「低山」に関連したテーマでもう一話。
そもそも「山」とはなんだろう。例によって『広辞苑』(岩波書店)を紐解くと、「平地よりも高く隆起した地塊。谷と谷との間にはさまれた凸起地」と定義しているが、我々登山者にとっては、国土地理院の2万5000分の1地形図に山名と標高が書かれているものが「山」と理解したい。
「日本一高い山」は、幼児以外の日本人なら誰でも知っている富士山(3776m)だが、では、「日本一低い山」はどこにあり、なんという山かご存じだろうか。結論から先に言うと、宮城県仙台市宮城野区蒲生にある日和(ひより)山(標高3m)である。仙台市の太平洋岸、蒲生干潟の西に位置し、初日の出の名所として知られる築山(明治時代末期、地元住民により人工的に土を盛り上げて造られた山)だ。ただし、この山に落ち着くまでには紆余曲折があった。
かつて地形図に載っている「日本一低い山」は、大阪市港区の安治川畔、天保(てんぽう)山公園にある天保山(4・53m)と言われてきた。天保2(1831)年から2年間、大坂湾から市中へ遡る安治川の浚渫工事の折に築かれたのがこの天保山で、当初は標高約20mだったという。山頂に二等三角点が設置されている。
ところが、平成5(1993)、天保山が地形図から抹消されたため、前記の日和山(6・05m)が「日本一低い山」の称号を得ることになった。しかし、逆転が起こり平成8(1996)年、地元からの要望があって天保山が地形図に復活、日本一に返り咲いたのである。
だが、これでは終わらなかった。平成23(2011)年3月11日の東日本大震災による地盤沈下と津波の直撃を受けた日和山が、蒲生干潟とともに消滅してしまったのである。日和山の消失を惜しんだ地元住民が砂利を積み上げて復活させたところ、平成26(2014)年、国土地理院の調査により標高3mの山と認定され、再逆転で日和山が日本一となったのである。
なお、天保山にあるのは二等三角点だが、一等三角点のある山として日本一低い山は、堺市堺区の大浜公園内にある蘇鉄山(7m)である。天保年間に築かれた御陰山(人工の築山)が削られたため、昭和14(1939)年、一等三角点が大浜公園の築山である蘇鉄山に移設されたものである。
ところで、以上3つの山々は全て人工の築山である。それでは、自然の山で「日本一低い山」はどこにあるのだろうか。地形図に掲載されている〝自然の山″で日本一低いのは、徳島市方(かたの)上(かみ)町にある弁天山(6・07m)だ。弁天山保存会が結成され、標高にちなんで毎年6月1日(小数点以下四捨五入)に山開きが催される。筆者も登頂してきたが、登頂証明書(有料)も発行されているというこだわりようだった。
■バックナンバー
 好奇心は旅の素
好奇心は旅の素 あえてインコンビニエンスな世界へ
あえてインコンビニエンスな世界へ 野外体験と道具
野外体験と道具 植村直己さんは臆病だった!?
植村直己さんは臆病だった!? イギリスの旅から(上)
イギリスの旅から(上) イギリスの旅から(中)
イギリスの旅から(中) イギリスの旅から(下)
イギリスの旅から(下) アメリカ北西部の3つの国立公園をめぐる旅から(1)
アメリカ北西部の3つの国立公園をめぐる旅から(1) アメリカ北西部の3つの国立公園をめぐる旅から(2)
アメリカ北西部の3つの国立公園をめぐる旅から(2) アメリカ北西部の3つの国立公園をめぐる旅から(3)
アメリカ北西部の3つの国立公園をめぐる旅から(3) アメリカ北西部の3つの国立公園をめぐる旅から(終)
アメリカ北西部の3つの国立公園をめぐる旅から(終) 「登りたい山」と「登れる山」とのミスマッチ
「登りたい山」と「登れる山」とのミスマッチ 燕岳に見た多様化する登山者像
燕岳に見た多様化する登山者像 害虫の食害で蔵王山の樹氷がピンチ
害虫の食害で蔵王山の樹氷がピンチ ポスト・コロナで「低山ブーム」到来か
ポスト・コロナで「低山ブーム」到来か 「日本一低い山」はどこに?
「日本一低い山」はどこに?■著者紹介
節田 重節(せつだ じゅうせつ)
日本ロングトレイル協会 会長
1943年新潟県佐渡市生まれ。中学時代に見た映画『マナスルに立つ』や高校時代に手にしたモーリス・エルゾーグ著『處女峰アンナプルナ』を読んで感激、山登りに目覚める。明治大学山岳部OB。㈱山と溪谷社に入社、40年間、登山やアウトドア、自然関係の雑誌、書籍、ビデオの出版に携わり、『山と溪谷』編集長、山岳図書編集部部長、取締役編集本部長などを歴任。取材やプライベートで国内の山々はもとより、ネパールやアルプス、アラスカなどのトレッキング、ハイキングを楽しむ。トム・ソーヤースクール企画コンテスト審査委員。日本ロングトレイル協会 会長、公益財団法人・植村記念財団理事など登山・アウトドア関係のアドバイザーを務めている。