
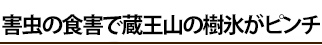

著者 節田 重節
「陸奥をふたわけざまに聳えたまふ蔵王の山の雲の中にたつ」
山形県南村山郡金瓶村(現・上山市)出身の歌人・斎藤茂吉の歌碑が、蔵王山の主峰・熊野岳(1841m)山頂に立つ。ちなみに蔵王山という名称の山はなく、熊野岳を主峰として宮城県と山形県にまたがる火山群の総称である。
7月下旬、その蔵王山に登ってきた。前夜は宮城側にある峩々温泉(ががおんせん)で山峡の名湯を満喫。翌日、タクシーで刈田岳(1758m)に上がり、馬ノ背から蔵王のシンボル、御釜を見下ろしながら熊野岳へ。山頂から地蔵山(1736m)を経てロープウェイの地蔵山頂駅に下山したのだが、付近の山肌を見て愕然とした。蔵王名物の「樹氷」の基となるオオシラビソ(アオモリトドマツ)がすっかり丸裸になり、死屍累々といった惨状であった。山頂駅で乗ったロープウェイ車内から見下ろした光景も惨憺たるもので、話には聞いていたが実に痛々しい姿だった。
 「樹氷」とは、過冷却水滴(氷点下になってもまだ凍っていない微小水滴)が針葉樹に吹き付けられて凍り付く現象で、樹木全体を覆ったものは「スノーモンスター(アイスモンスター)」と呼ばれる。多量の過冷却水滴と雪が常に一定方向からの強風で運ばれてくることが条件で、風上に向かって発達するので、「エビの尻尾」と同じもの。東北の山に多く、蔵王山のほか八甲田山や八幡平、森吉山、西吾妻山などがその名所として挙げられる。
「樹氷」とは、過冷却水滴(氷点下になってもまだ凍っていない微小水滴)が針葉樹に吹き付けられて凍り付く現象で、樹木全体を覆ったものは「スノーモンスター(アイスモンスター)」と呼ばれる。多量の過冷却水滴と雪が常に一定方向からの強風で運ばれてくることが条件で、風上に向かって発達するので、「エビの尻尾」と同じもの。東北の山に多く、蔵王山のほか八甲田山や八幡平、森吉山、西吾妻山などがその名所として挙げられる。地元ではマタギなどが「雪の坊」と呼んでいたそうだが、「樹氷」と命名したのは旧制山形高等学校教授(のちに山形大学教授)で、蔵王火山の地質学的研究者として知られる安斎徹である。
「樹氷と言えば蔵王、蔵王と言えば樹氷」として有名だが、その蔵王の樹氷がピンチを迎えている。2013年に蛾の一種、トウヒツヅリヒメハマキの幼虫が大量発生し、冬に樹氷を形作るオオシラビソの葉裏を食害するという被害を引き起こした。16年にはほぼ終息したが、樹勢が衰えた木にトドマツノキクイムシが入り込んで内部を食い荒らし、枯死被害が急速に広がっているのだ。
東北森林管理局の調査によると、標高約1600mの蔵王ロープウェイ地蔵山頂駅周辺は、約16㏊にわたって枯死木のみの状態になっており、被害本数は約6700本という。蔵王山全体の被害分布域は約700㏊で、その範囲で約2万3000本が枯死しているのが確認された。生きている木は約12万6000本だったとのこと。確かに我々が上がってきた蔵王エコーラインの宮城・山形県境周辺も被害が目立っていた。
冬の観光の目玉である樹氷が消えては、地元にとっても、我々登山者やスキーヤーにとっても一大事である。アオモリトドマツ林の再生を目指す官民一体の組織「樹氷復活県民会議」を中心に、地元新聞社や放送局も協力して復活作戦がスタートしている。山形森林管理署は19年度から、被害が少ない標高1400m地点で自生する稚樹を山頂駅そばの林地に植え替える試験を始めており、今後は民間の力を借りて稚樹の採取や移植活動に取り組んでいく考えである。
なお、地蔵山付近で樹氷原を形作っているオオシラビソの枯死は、ただちに樹氷の消滅を意味するものではなく、実際、立ち枯れた木にも樹氷は発生している。したがって、枯れた幹が朽ち果てるのに要する年月が過ぎたのちに、樹氷が姿を消すことになろう。専門家はその年数を10年以上と見ており、次第に幹が倒伏していくことで樹氷原が失われ、広大な雪原が広がることになるだろうと予想している。
樹氷は暖かくてはできず、寒過ぎても発生しないとのこと。近年の地球温暖化も影響しているとの見立てもあるが、樹氷原のない蔵王山は想像したくない。なんとか現状で踏みとどまってもらい、世界的にも珍しい自然現象を守っていきたいものである。
■バックナンバー
 好奇心は旅の素
好奇心は旅の素 あえてインコンビニエンスな世界へ
あえてインコンビニエンスな世界へ 野外体験と道具
野外体験と道具 植村直己さんは臆病だった!?
植村直己さんは臆病だった!? イギリスの旅から(上)
イギリスの旅から(上) イギリスの旅から(中)
イギリスの旅から(中) イギリスの旅から(下)
イギリスの旅から(下) アメリカ北西部の3つの国立公園をめぐる旅から(1)
アメリカ北西部の3つの国立公園をめぐる旅から(1) アメリカ北西部の3つの国立公園をめぐる旅から(2)
アメリカ北西部の3つの国立公園をめぐる旅から(2) アメリカ北西部の3つの国立公園をめぐる旅から(3)
アメリカ北西部の3つの国立公園をめぐる旅から(3) アメリカ北西部の3つの国立公園をめぐる旅から(終)
アメリカ北西部の3つの国立公園をめぐる旅から(終) 「登りたい山」と「登れる山」とのミスマッチ
「登りたい山」と「登れる山」とのミスマッチ 燕岳に見た多様化する登山者像
燕岳に見た多様化する登山者像 害虫の食害で蔵王山の樹氷がピンチ
害虫の食害で蔵王山の樹氷がピンチ■著者紹介
節田 重節(せつだ じゅうせつ)
日本ロングトレイル協会 会長
1943年新潟県佐渡市生まれ。中学時代に見た映画『マナスルに立つ』や高校時代に手にしたモーリス・エルゾーグ著『處女峰アンナプルナ』を読んで感激、山登りに目覚める。明治大学山岳部OB。㈱山と溪谷社に入社、40年間、登山やアウトドア、自然関係の雑誌、書籍、ビデオの出版に携わり、『山と溪谷』編集長、山岳図書編集部部長、取締役編集本部長などを歴任。取材やプライベートで国内の山々はもとより、ネパールやアルプス、アラスカなどのトレッキング、ハイキングを楽しむ。トム・ソーヤースクール企画コンテスト審査委員。日本ロングトレイル協会 会長、公益財団法人・植村記念財団理事など登山・アウトドア関係のアドバイザーを務めている。