


- 第9回 -著者 小西 浩文
歩き方、ちょっとした動作で、身体能力が分かる
ひたすら、ひたすら、ゆっくりと上がって行く。風が吹いているなか、西田さんの呼吸をはかる。西田さんのスタンスを頭の中に叩き込んで、決して、無理なステップでは上がらない。使う筋肉以外は、休ませながら、登る。殆どの人達が、日常の動作でも、使わなくてもいい筋肉に力を入れている。
例えば、食事の時、箸を持つ場合でも、必要以上に力んでいる場合がある。電車の吊り革を持つ場合でも、また、歩く時でも然り。こういう身体の動きは、*丹田呼吸と同様、しょっちゅう気を遣っていないと、身には付かない。いつの頃からか、私には、その人の歩き方、ちょっとした動作で、身体能力が分かる様になってきた。これは殆どの場合、生まれ持った素質が、極めて大きなウエイトを占める。
呼吸は、吐くことのみに集中する
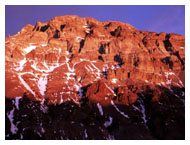 もし、身ごなしが硬い場合には、心身の鍛錬を続けていくうちに克服せねばならないものと、私は思っている。西田さんは、役者だけあって、身体の使い方は完全に身についていた。呼吸法については、吐くことのみに集中してくださいと教えていた。きちんと吐けば、自然に呼吸は出来る。その呼吸も、必ず、登り降りのステップのペースに合わせる。
もし、身ごなしが硬い場合には、心身の鍛錬を続けていくうちに克服せねばならないものと、私は思っている。西田さんは、役者だけあって、身体の使い方は完全に身についていた。呼吸法については、吐くことのみに集中してくださいと教えていた。きちんと吐けば、自然に呼吸は出来る。その呼吸も、必ず、登り降りのステップのペースに合わせる。 ステップと呼吸がバラバラになれば、それだけ早くバテてしまう。呼吸に集中して、登ることに集中していれば、時々、無念無想の境地に入ることがある。比叡山の千日回峰行をはじめとした、日本の密教等の修行が、山をひたすら歩くのみという形態をとっていることも、うなずけるものがある。しかし、高い山を登る場合には、なかなかそこまで歩くことのみに集中することが出来ない。何故か、それは、外的危険が多過ぎるからである。
ヒマラヤの高峰であれば、雪崩、落石、クレバス(氷河の割れ目)、雪庇の崩壊等、そして転落やスリップなど。アコンカグアでは高度障害に加えて、凍傷、スリップ、落石などの危険があった。こういう危険を見分けたり、対処するのは視床下部である。密教、ラマ教などでは<第三の眼>と言われている箇所である。この視床下部が鈍っていたり、混乱していると、危険を感知したり、回避することは出来なくなる、と言ってもよい。
宮本武蔵は視床下部が発達していた
昔の剣豪、例えば上泉伊勢守信網、柳生石舟斎、宮本武蔵など、殆ど怪我をせずに、幾多の真剣勝負を勝ち抜いて、生き抜いた人達は、極度に視床下部が発達していたのであろうと、私は思っている。兵法の教えに「観の眼つよく、見の眼よわく」という言葉がある。これは、心の眼ではしっかり観て、実際の眼で見えるものには決してこだわらず、という教えである。この場合の「観の眼」というのが視床下部のことであると、私は、考えている。非常に高い山を登る場合に、この視床下部が、極めて、重要になってくることは言うまでもない。これは、持って生まれたものに加えて、生死のかかった真剣勝負の経験が重要になってくる。
「小西っ、生命は、預けるぜっ」と西田さんが言った
あと、もう一つ、兵法の教えに「武の極意」というのがある。これは、「武の極意は、経験にあり。よって経験することを恐るべからず」という教えである。これは、極限を追求する山登りにも、極意となる教えである。しかし、この教えには、実は大問題がある。それは経験を積んでいくうちに、その過程で、死んだり、怪我をする可能性が、極めて高いということである。しかし、生きるか死ぬかの経験を、幾多も乗り越えないと、本物にはなれない。ここにやり直しのきかない、生死のかかった真剣勝負の厳しさ、難しさが、あった。今回のアコンカグアで、西田さんが、ベースキャンプで出発時に言った言葉がある。それは、「小西っ、生命は、預けるぜっ」という言葉だった。
私は、登りながら、西田さんを含めた、全員のコンディション、そして、アコンカグアのコンディションを、「観の眼」で、読み取ろうとしていた。
※注 丹田 下腹のこと
■バックナンバー
 世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(1)
世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(1) 世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(2)
世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(2) 世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(3)
世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(3) 世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(4)
世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(4) 世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(5)
世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(5) 世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(6)
世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(6) 世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(7)
世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(7) 世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(8)
世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(8) 世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(9)
世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(9) 世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(10)
世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(10) 世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(11)
世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(11) 世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(12)
世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(12) 世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(13)
世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(13) 世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(14)
世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(14) 世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(15)
世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(15) 世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(16)
世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(16) 世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(17)
世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(17) 世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(18)
世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(18) 世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(終)
世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指す私の夢(終)■著者紹介
小西浩文(こにし ひろふみ)
1962年3月15日石川県生まれ。登山家。
■登山歴
1977年 15歳で本格的登山を始める
1982年 20歳でパミールのコルジュネフスカヤ、コミュニズムに連続登頂
1982年 中国の8000m峰シシャパンマに無酸素登頂
1997年 7月ガッシャブルム1峰(8068m)無酸素登頂に成功し、日本最高の8000m6座無酸素登頂を記録
2002年 世界8000m峰全14座無酸素登頂を目指して活動中
☆ 世界8000m峰14座無酸素登頂記録保持者は現在2人。メスナー(イタリア)とロレタン(スイス)のみ
☆ 89年のハンテングリ登頂により、日本人初のスノーレオパルド(雪豹)勲章の受賞が決定するが、ソ連崩壊により授章式は行われず
■その他
1986年 東宝映画「植村直巳物語」出演
1986年 フジTVドラマ「花嫁衣裳は誰が着る」岩登りアドバイザー
1988年 VTR「最新登山技術シリーズ全6巻」技術指導及び実技出演
1993年 日本TV「奥多摩全山24時間耐久レース」出演
1999年 NHK「穂高連峰の四季~標高3,000