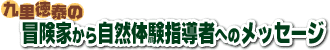
- 第6回 - 著者 九里 徳泰
「教育としての自然体験活動」
自然体験は目的達成のための手段
 今回は、自然体験活動の目的とは何だろうか、ということえを考えてみたい。
今回は、自然体験活動の目的とは何だろうか、ということえを考えてみたい。体験そのものに目的があるという考え方もあるが、せっかくやるのなら成果をしっかり評価したい。同じ自然体験のプログラムでも、目的しだいで成果は大きく変るものだ。
その目的とは、子どもの主体性の確立や、物事を切り開くという意味での冒険マインドの育成や、自然と触れあうことでの環境への知識を高めることや、人と協調して行動する能力を身につけるとか、いろいろある。
前の号にも書いたが、自然体験はその目的達成のための1つの「手段」にすぎない。だから、指導者は安易に、自然体験そのものを楽しむことにエネルギーを注ぎすぎてはいけない。自然体験は、遊びを通しての教育ととらえてもかまわないが、けっして単なる遊びではない。目的が明確にあるものである、ということを考えて欲しい。
統制位置の変化
私が、昨年長野県白馬村で行った、「2002年環境冒険国際キャンプ」には、36人の小中学生が集まったが、それには大きな目的があった。子どもが集まって自主的にキャンプをするという体育的な発想でなく、自然体験という”手法”を使って、教育的な目的を達成することにあった。だから、3ヶ月前からプログラム制作には念には念を入れた。
私たち団体の大きな目標は、心理学で言う「統制位置の変化」を子どもに持たせること、とが一義にあり、私たちなりの環境、冒険、国際というトリプルボトムライン(*下記注)を実践することだ。
統制位置の変化とは難しそうに聞こえるが、○○がいけないからできないと、他者のせいにしている、行動にひっこみがちの子どもたちを、自分で発言し、行動できる態度にキャンプを通じて変容することができるか、ということだ。
大命題は、「環境」、「冒険」、「国際」
その大命題のもとに、3つのボトムラインをきめた。
「環境」、「冒険」、「国際」である。
この内容は、指導者の思うところでいい。私たちが考えたのはこの要素だった。
環境では、姫川という川を源流から河口まで60Km歩いてたどることと、森の間伐をして、水の循環を体験的に理解した。
冒険では、自分の未知の領域への体験をした。1日20Km以上、ザックを背負って歩く、自活して生活する、2000mの登山を子どもだけの意志で行うというもの。
最後の国際は、昨今の国際理解教育を念頭に、1/3を、外国人、もしくは国外の在留邦人経験者として外国の文化、外国語のほうが得手という子どもと、日本国内で育った子どもとの交流をキャンプ生活を通じて行った。
統制位置の変化については現在調査中だが、多くの子どもが変化の兆しを見せた。
環境、冒険、国際に関しては、皆肌身を通して感じていることがわかる作文が送られてきた。これぞ、自然体験を通しての教育の醍醐味だろう。
*トリプルボトムライン
日本の企業は欧州型といわれる、TBL(トリプルボトムライン)を守りましょうという方向に動いている。トリプルボトムラインとは、企業がこれまで推し進めてきた、経済性追求だけでなく、社会、環境も取り込んだ経営をするべきだという議論である。
では、自然体験活動におけるトリプルボトムライン=やるべき問題点とはなんだろうか、というのが議論になるべき点だろう。
■バックナンバー
 冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(1)
冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(1) 冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(2)
冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(2) 冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(3)
冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(3) 冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(4)
冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(4) 冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(5)
冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(5) 冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(6)
冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(6)■著者紹介
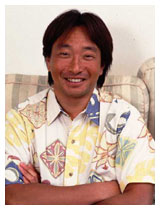 九里 徳泰(くのり のりやす)
九里 徳泰(くのり のりやす)1965年生まれ。冒険家、中央大学助教授。中央大学大学院総合政策研究科修了。
冒険家として世界80カ国を訪問。チベット高原自転車縦断、南米アコンカグア自転車下降などを学生時代に行う。その後も、高所登山、カヌー、自転車とオールラウンドにアウトドアでの冒険を展開。1997年に7年間にわたるアメリカ大陸人力縦断でオペル冒険大賞エポック賞受賞。
近著に、 「親と子の週末48時間」(小学館)、「九里徳泰の冒険人類学」(同朋舎)など、著作多数。作家、テレビ・ラジオ・インターネットメディアの出演者として多方面に活動している。
■関連情報
 九里徳泰HP
九里徳泰HP 中央大学研究開発機構
中央大学研究開発機構 中央大学研究開発機構(政策科学研究ユニット)
中央大学研究開発機構(政策科学研究ユニット)