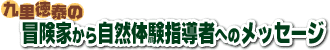
- 第2回 - 著者 九里 徳泰
自分が感銘を受けた体験をプログラムにフィードバックする
自然体験指導者が実際に体験教育を行う際にはプログラム策定を行うが、その場合に1つ考えてほしい。
プログラムをしなくてはいけないという、時間的制約の中から、既存の自然体験プログラムを安直に採用することはちょっと待ってほしい。
「自分が感銘を受けた自然体験」を、ソファーに座ってコーヒーでも飲みながらゆるやかに考えてみて欲しい。
そして、次に自らが実際の自然の中で感銘を受けたことを、どのようにプログラムに入れ込んでいくことをお見えがいて欲しい。
あの、感動体験をどうやってみんなに伝えようか・・・・ということである。
私は、自然体験指導者はだれでもできてしまう職能だとは思わない。自然の中での、気づき、発見、そして感動をおぼえたものが、やる仕事である。
 自然の中での感銘はどんな小さなことでもいい。
自然の中での感銘はどんな小さなことでもいい。ひとりぼっちでテントで寝たときのこと。
大汗をかいて山に登って、見た下界の景色。
自転車で100Km走りきった、あの爽快感。
子供どものころのことでもかまわない。
自然体験指導者の役割は、そのような”自分”で感じた、その瞬間をどう伝えるかではないだろうか。
そのような指導員が体験したことを、生徒、対象者に伝えることにこそリアリティのある教育効果の高いプログラムになる。
それでは、既存のプログラムにどのように、組み込めばいいのであろうか?
以下のように3段階で、プログラムを組んでみるといい。
ミッション:
手法:
評価:
ミッションとは、そのプログラムの目的、伝えたいこと
手法、とはどのような方法とどのような場所、道具を使いながらするのか、
評価、とはその方法がミッションに対して、効果的であるかを考えるということだ。
どれだけいいミッションも、やり方=手法が悪ければ、いいプログラムとはいえない。
ここで重要なのは、教育と遊びをごっちゃにしない、ということだ。楽しいプログラムと、遊び(ミッションが、単純なレジャー)とは、大きな違いがあるということだ。
あるものを、疑問なく使うのではなく、指導者の産みの苦しみがあってこその、その創造への楽しみこそが、多様な人間とその自然体験を支えるのでは、ないのであろうか。
■バックナンバー
 冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(1)
冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(1) 冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(2)
冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(2) 冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(3)
冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(3) 冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(4)
冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(4) 冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(5)
冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(5) 冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(6)
冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(6)■著者紹介
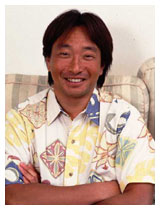 九里 徳泰(くのり のりやす)
九里 徳泰(くのり のりやす)1965年生まれ。冒険家、中央大学助教授。中央大学大学院総合政策研究科修了。
冒険家として世界80カ国を訪問。チベット高原自転車縦断、南米アコンカグア自転車下降などを学生時代に行う。その後も、高所登山、カヌー、自転車とオールラウンドにアウトドアでの冒険を展開。1997年に7年間にわたるアメリカ大陸人力縦断でオペル冒険大賞エポック賞受賞。
近著に、 「親と子の週末48時間」(小学館)、「九里徳泰の冒険人類学」(同朋舎)など、著作多数。作家、テレビ・ラジオ・インターネットメディアの出演者として多方面に活動している。
■関連情報
 九里徳泰HP
九里徳泰HP 中央大学研究開発機構
中央大学研究開発機構 中央大学研究開発機構(政策科学研究ユニット)
中央大学研究開発機構(政策科学研究ユニット)