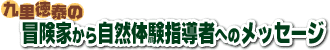
- 第3回 - 著者 九里 徳泰
「地球環境とアウトドア」
歴史的に見ると、アウトドアへのアプローチは日本の場合、山からスタートしている。山はまず信仰対象として、修験者により登られ、のちにヨーロッパ的なスポーツ、近代登山として日本に上陸する。
アウトドア、特にウイルダネスという、人の足跡すらついてない場所に立ち入ることは、神の領域すら犯す行為で、紀元前しばしば行われた人間と強い神との戦い、という様相もあった。頂上攻撃(アッタク)や幕営(キャンプ)、遠征(エクスペディション)など、戦争用語がその名残だ。
しかし、多くの自然への侵略は、人間の冒険心・探検心は向上させたが、脆弱な手つかずの自然・ウイルダネスを、荒らしてしまうという結果となってしまった。
世界最高峰のエベレストに横たわる何百本にわたる廃棄された酸素ボンベの姿は1つの象徴だ。
時代は、大きく変った。最近の話題は、経済的な不況はさることながら、ダムや堰の問題、温暖化、稀少生物などの問題も大きな関心事である。アウトドアは、単に冒険や挑戦の場所でなく、人類の資産としての自然を守る場所へと変容している。
では、冒険家として、アウトドアの携わるものとしてどのようにアウトドアに接すればいいのだろうか?
資本主義という、おおきな経済システムの中で何が我々にできるのだろうか?
 「社会とは本来、優れた知識や情報を持つ人間が、勝利者となるものである。しかし、私たちの社会はといえば、決して公平とはいえないのだ。私たちは相手が仕掛けてくる戦いと、同じやり方で戦う必要がある。私たちはもっと賢く、もっと想像的になるべきである。そして、成功につながる革命の始まりは、トップからではなく、すべて下から起ったのだという事実を忘れてはならない」- イヴォン・シュイナード、パタゴニアオーナー
「社会とは本来、優れた知識や情報を持つ人間が、勝利者となるものである。しかし、私たちの社会はといえば、決して公平とはいえないのだ。私たちは相手が仕掛けてくる戦いと、同じやり方で戦う必要がある。私たちはもっと賢く、もっと想像的になるべきである。そして、成功につながる革命の始まりは、トップからではなく、すべて下から起ったのだという事実を忘れてはならない」- イヴォン・シュイナード、パタゴニアオーナーアメリカにはグラスルーツという考え方がある。日本語にすると”草の根”。とはいえ、NPOやNGOを造って反対運動を起こせばいいという話ではない。アウトドズマンは、他の人よりもアウトドアを知っている。アウトドアズマンこそ地球の生態系や自然の破壊に対して、グラスルーツの意識を持つことではないだろうか、という考えを持つことが必要ではないだろうか。
■バックナンバー
 冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(1)
冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(1) 冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(2)
冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(2) 冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(3)
冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(3) 冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(4)
冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(4) 冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(5)
冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(5) 冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(6)
冒険家から自然体験指導者へのメッセージ(6)■著者紹介
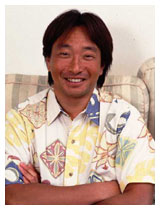 九里 徳泰(くのり のりやす)
九里 徳泰(くのり のりやす)1965年生まれ。冒険家、中央大学助教授。中央大学大学院総合政策研究科修了。
冒険家として世界80カ国を訪問。チベット高原自転車縦断、南米アコンカグア自転車下降などを学生時代に行う。その後も、高所登山、カヌー、自転車とオールラウンドにアウトドアでの冒険を展開。1997年に7年間にわたるアメリカ大陸人力縦断でオペル冒険大賞エポック賞受賞。
近著に、 「親と子の週末48時間」(小学館)、「九里徳泰の冒険人類学」(同朋舎)など、著作多数。作家、テレビ・ラジオ・インターネットメディアの出演者として多方面に活動している。
■関連情報
 九里徳泰HP
九里徳泰HP 中央大学研究開発機構
中央大学研究開発機構 中央大学研究開発機構(政策科学研究ユニット)
中央大学研究開発機構(政策科学研究ユニット)