
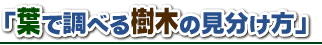

~ 夏編2「ウツギ」 ~ 著者 林 将之
■たくさんある「ウツギ」と名の付く木
| 樹木を覚え始めると、「ウツギ」と名の付く木がたくさんあることに気付きます。ノリウツギ、タニウツギ、フジウツギ、コゴメウツギ・・・ウツギの仲間はずいぶん種類が多いんだなぁ、と思ってしまいますが、じつは上に挙げた4種はいずれも別の仲間です。ノリウツギはユキノシタ科、タニウツギはスイカズラ科、フジウツギはフジウツギ科、コゴメウツギはバラ科・・・こうなるとますます混乱して、しまいには「ウツギって嫌な仲間だ」というふうに敬遠したくもなる気持ちも分かります。そこで今回は、このややこしい「ウツギ」と名の付く木について整理してみましょう。 |  ハナツクバネウツギ(アベリア)の茎 |
|
種名
|
花期
|
属名
|
科名
|
| ウツギ |
5~7月
|
ウツギ属
|
ユキノシタ科
|
| マルバウツギ |
4~5月
|
||
| ヒメウツギ |
4~5月
|
||
| バイカウツギ |
6~7月
|
バイカウツギ属
|
|
| ノリウツギ |
7~9月
|
アジサイ属
|
|
| ガクウツギ |
5~6月
|
||
| コガクウツギ |
6~7月
|
||
| タニウツギ |
5~6月
|
タニウツギ属
|
スイカズラ科
|
| ニシキウツギ |
5~6月
|
||
| ハコネウツギ |
5~6月
|
||
| ヤブウツギ |
5~6月
|
||
| キバナウツギ |
4~5月
|
||
| ツクバネウツギ |
5~6月
|
ツクバネウツギ属
|
|
| ハナツクバネウツギ |
6~10月
|
||
| フジウツギ |
7~8月
|
フジウツギ属
|
フジウツギ科
|
| ドクウツギ |
4~5月
|
ドクウツギ属
|
ドクウツギ科
|
| ミツバウツギ |
5月
|
ミツバウツギ属
|
ミツバウツギ科
|
| コゴメウツギ |
5~6月
|
コゴメウツギ属
|
バラ科
|
|
■ユキノシタ科・スイカズラ科の2大勢力 正真正銘の「ウツギ」という木はあるのでしょうか? 正真正銘かどうかは分かりませんが、単にウツギ(別名ウノハナ)という名の木は存在します。ユキノシタ科ウツギ属の落葉低木で、身近な山野に多く見られる木なので、最も正統なウツギに相応しいと言えます。同じユキノシタ科にはマルバウツギ、ヒメウツギ、ノリウツギ、ガクウツギなどがあるように、ユキノシタ科は「ウツギ」と名の付く木をたくさん含む大派閥です。この中のノリウツギ、ガクウツギ、コガクウツギは、アジサイと非常に近い仲間で、花の形もガクアジサイと似ています。アジサイは「ウツギ」の名こそ付かないものの、やはり茎の中は立派な空洞になります。 ユキノシタ科に対抗する勢力にスイカズラ科があります。スイカズラ科はタニウツギ属とツクバネウツギ属という2軍を備え、両軍とも多くの「ウツギ」を含んでいます。ニシキウツギ(二色空木)やハコネウツギは、白とピンクの2色の花を咲かせる(正確には一つの花が白からピンクへ変わる)ため人気があり、庭木にも多く植えられています。また、ツクバネウツギの仲間から作られた園芸品種ハナツクバネウツギ(別名ハナゾノツクバネウツギ)は「アベリア」の名で親しまれ、こちらも公園などに多く植えられています。 ユキノシタ科とスイカズラ科の2大勢力以外にも、「ウツギ」と名の付く木はいくつかの科に点在しています。何ウツギと何ウツギが同じ仲間なのか、それをしっかり頭の中にたたき込んでおくと整理しやすくなります。花の時期も初夏のものが多いので、今咲いている「ウツギ」は何ウツギか確認してみましょう。 ■ウツギ類を見分ける特徴を探そう 仲間は違うけど、いろいろあるウツギ類。これらをうまく見分けるポイントは何でしょうか。幸いなことに、ウツギ類にはいくつかの共通点があります。一つめは、ほぼすべてが落葉低木であること(高木はない)、二つめは、コゴメウツギを除くすべての葉は対生(たいせい)につくこと、三つめは、コゴメウツギとミツバウツギを除くすべての葉は切れ込みのない単葉(たんよう)であることです。つまり、切れ込みのない単葉が対生する落葉低木を見つけた場合、枝を折ってみて中が空洞だったらウツギ類が有力と考えられます。ただし、若い枝は中が詰まっていることもあるし、「ウツギ」と名が付かない木でも空洞になっている種類もあるので注意が必要です。 葉の大きさ順に見てみましょう。 ● 最も小さな3~4cm程度の葉を持つのはツクバネウツギ属の仲間とコガクツウギ。ツクバネウツギの近縁種にはコツクバネウツギ、オオツクバネウツギなどもあります。コガクウツギは西日本で多く見られる木で、葉は細長い形です。 ● 続いておよそ5~7cmぐらいの葉を持つのがウツギ属の仲間、バイカウツギ、ドクウツギ。ウツギとドクウツギはかなり細長い形ですが、バイカウツギやマルバウツギは丸みを帯びた卵形です。主に北日本に分布するドクウツギは、猛毒を含む植物としても知られています。 ● さらに細長い葉を持つのがフジウツギ。10~15cmを超える細長い形で、よく庭木にされるブッドレア(フサフジウツギ)もこれと同じ仲間です。 ● そして最も幅広い葉を持つのはタニウツギ属の仲間とノリウツギです。時に15cmにもなるハコネウツギやノリウツギの葉を最大として、ニシキウツギ、ヤブウツギ、タニウツギなどの葉も10cm前後の大きさになります。 ●ウツギ類の中で特殊な葉を持つのがコゴメウツギとミツバウツギです。コゴメウツギは葉に浅い切れ込みがあり、林内に群生して生えるので一見キイチゴの仲間と見間違えそうですが、トゲはありません。ミツバウツギは名の通り3枚ワンセットの葉(三出複葉:さんしゅつふくよう)を持ち、若葉やつぼみは山菜として食べられます。 |
|
そうは言われても、やっぱり「ウツギ」と名の付く木は種類が多くてややこしいですね。ウツギ属、タニウツギ属、ツクバネウツギ属などの仲間を正確に見分けるには、葉裏の毛の有無や花の形状などを細かく確認する必要があります。これらウツギ類をちゃんと見分けられるようになれたら植物博士(マニア?)の仲間入りです。
アウトドアのプログラムにおいては、ウツギ類の茎の空洞を確かめてみると同時に、なぜ空洞があるのかを考えてみるのも面白いでしょう。一説には、少ないエネルギーで丈夫な構造の茎を作るためと言われています。より強固な構造を必要とする高木や、成長の遅い常緑樹では、このような空洞がほとんど見られないこととも何か関係がありそうです。
■バックナンバー
 葉で調べる樹木の見分け方 ~冬編1「基礎・冬芽」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~冬編1「基礎・冬芽」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~冬編2「冬の落葉樹」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~冬編2「冬の落葉樹」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~冬編3「常緑低木」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~冬編3「常緑低木」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~春編1「サクラ」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~春編1「サクラ」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~春編2「タラノキ」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~春編2「タラノキ」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~春編3「カエデ」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~春編3「カエデ」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~夏編1「ウルシ」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~夏編1「ウルシ」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~夏編2「ウツギ」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~夏編2「ウツギ」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~夏編3「掌状複葉」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~夏編3「掌状複葉」~ 葉で調べる樹木の見分け方 ~秋編1「どんぐり」~
葉で調べる樹木の見分け方 ~秋編1「どんぐり」~■著者紹介
 林 将之(はやし まさゆき)
林 将之(はやし まさゆき)1976年山口県生まれ。編集デザイナー。
千葉大学園芸学部卒業後、植生調査や造園系雑誌編集の職歴を経てフリーに。2002年、学校法人中央工学校 非常勤講師。葉で樹木を見分けることをテーマに掲げ、樹木の観察指導やデジタル標本収集等に取り組んでいる。現在運営する樹木鑑定サイト「このきなんのき」では投稿写真から樹木の名前の鑑定を行っている。
著書「葉で見わける樹木」(小学館)
■関連情報
 樹木鑑定サイト「このきなんのき」
樹木鑑定サイト「このきなんのき」





