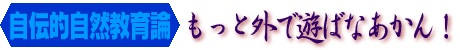
- 最終回 - 著者 高田 直樹
ウナギ取り
細い篠竹の先に付けた鉄砲みみず(太いみみず)を流れの上手から、岩の下にそろりと差し込んだ叔父は、「食った」と張りつめた小声でいいました。
そうっと、竹棒を引き抜いて、ミミズから伸びている糸を岩の上に置くと、
「一服して待とか、ナオキ。しっかり飲み込んでもらわんとあかんしな」
鉄砲ミミズの中には、半分に折った3センチ長の太い木綿ばりが忍ばしてあるのです。
流れの真ん中のその岩の上に腰を下ろすと、叔父はたばこに火をつけました。小さい子供のぼくも、並んで平らな岩の端に座りひざを抱えました。
ぼくは、叔父につれられて村を流れる川にウナギ取りに来ていたのです。
やがて立ち上がった叔父は、糸を手に巻くと、パンと激しく引っ張りました。その瞬間木綿ばりは、ウナギの腹中にかんぬきのように突き刺さります。激しい痛みにもかかわらず、ウナギはしっぽを巻き付けてがんばり、出てこようとはしません。篠竹で繰り返し突つかれたウナギは、とうとう姿を現しました。ぼくの腕ほどもある真っ黒の大ウナギは、叔父の腕の下で跳ね踊ったのです。
鮎掛け
高校生の頃には、同じ川で素潜りで〈鮎掛け〉をしたものです。仕掛けはやはり篠竹で、自作しました。友釣り用の釣り針に木綿糸をつけます。1メートル位の篠竹には端から数センチのところに切り込みをいれ、30センチくらいのところに、糸の一端に着いた竹べらを固定する仕掛けを作ります。
鮎掛け棒の先端には友釣り針があり、これで鮎を掛けると、その30センチほどの糸が伸びるという仕組みです。
鮎の腹に掛けるなどというのは、下手くそで、背びれの後ろ辺りを狙えるのが熟練者のすることでした。そうしないと獲物は死んでしまうし、激しく暴れて取込みで傷を大きくしてしまいます。
鮎には、その縄張り意識が強い所為か、同じ経路を繰り返し通るという習性があります。
狭い渓流では、1~3メートル位の輪を書いて回り続けたり、あるいは単純に往復運動を繰り返します。だから一度通った地点を必ずまた通ることになります。
水中で待ち伏せる。素潜りで待ち受けるには、必死に息こらえをしないといけません。来たと思った時に息が切れたりするのでした。
何度も何度も失敗を繰り返しながら、技術を磨く必要がありました。
いとおしむように手で掴む
〈鮎掛け〉は、本当に鮎との一騎討ちという感じで、ぼくは大好きでした。とは言え、鮎に殺されることはないので、対等な一騎討ちとはいえませんが。
夏の終わりともなると、そこまで生き延びて来た鮎は、したたかとなっています。
ある時、突如獲物の姿が消え、そんなことあり得ないと、しらみつぶしに探すと、なんとその鮎は、激しい流れに抗して、必死の形相で岩に張り付いていたのです。
ぼくはそ奴を見逃すことにしたのでした。
ぼくの父は、魚の手掴みの極意を、こんな風に語ったことがありました。
「時々、そっと中指を伸ばして探ってみる。スルっと魚に触れたら、もうしめたもんや。丸めた掌に、あっちから入ってくるんや」
捉えてやろうとか、掴んでやろうなどと考えていたら、なかなか難しい。いとおしむ如く手を差し伸べると、その中に吸い寄せられる様に入ってくる。
そんな風に分かって来たのは、それから大分後のことでした。
魚の手掴みで命の大切さを学んだ
あの叔父も、そして父も今はこの世の人ではありません。ぼくが貰った体験とか極意とかを、せめて孫にでも伝えたいと思っても、そういう環境が今の日本にはないことに思い至り、少々暗たんとした気分になるのです。
学童児童を、野外に連れ出して、「魚の手掴み」をやらせるという話を聞きました。
酸素を吹き込む水槽に入れられ、トラックで運ばれたイワナやあまごは、そのために掘られたくぼみのような池に流し込まれる。
歓声を上げて子供たちは、既に瀕死の魚を掴み上げるのでしょう。
そういう情景は、ぼくにはなにか強制収容所のガス室のように映ってしまうのです。
大昔、生き抜くための必死の営みであった採集、漁労、狩りなど行為を、安易なものとして教えてはならない。商業主義に利用されることに敏感でなければならない。
さもなくば、とんでもなく人間の生命をも軽んずる人間を作ることになるのではないだろうか。
そんな気がしてくるのです。
■バックナンバー
 もっと外で遊ばなあかん!(1)
もっと外で遊ばなあかん!(1) もっと外で遊ばなあかん!(2)
もっと外で遊ばなあかん!(2) もっと外で遊ばなあかん!(3)
もっと外で遊ばなあかん!(3) もっと外で遊ばなあかん!(終)
もっと外で遊ばなあかん!(終)■著者紹介
高田 直樹(たかだ なおき)
 1936年京都生まれ。京都府立大学卒。同大学山岳部OB。
1936年京都生まれ。京都府立大学卒。同大学山岳部OB。国際登山家。教育評論家。
大学卒業後、京都府立高等学校で化学の教鞭をとるかたわら、登山や教育についての執筆評論活動を行う。
主な登山活動は、厳冬期剣岳東大谷G1初登攀、積雪期前穂高岳屏風岩第1ルンゼ第2登など。
また、海外ではカラコルム、ネパール、旧ソ連コーカサス、中国など各地の未踏峰へ、隊長として数多くの登山隊の指揮をとる。中でも1979年のカラコルム、ラトックI峰(7,145m)の初登頂は世界的に知られている。
一方で、パソコンのデーターベース処理・開発の専門家としても著名。
現在、龍谷大学非常勤講師(教育情報処理)。
株式会社クリエイトジャパン取締役、Ez-Comsite France 社外取締役、
株式会社イージー・コムサイト 取締役。
著書
自伝的登山論『なんで山登るねん(正・続・続々)』(山と溪谷社)
体験的教育論 『いやいやまあまあ』(ミネルヴァ書房)
『入門 TURBO PASCAL プログラミング』(ソフトバンク社)
『dBaseIII PLUS ガイド』(ソフトバンク社)
『FRAMEWORKガイド』(ソフトバンク社)
『FRAMEWORKII EZ ガイド』(ソフトバンク社) など。
専門誌・雑誌他
1981年7月~9月京都新聞夕刊小説欄に92回の自伝的教育論『いやいやまあまあ』を連載。
1985年12月、NEC98ラップトップ機をネパール山中で初試用。『日経パソコン』誌の取材を受ける。ソフトバンク社『Oh!PC』1985年1月号特集・ボクの夢のパソコンに『ワープロが作家になる日』を執筆。1991年1月よりソフトバンク社『Oh! PC』誌上にエッセイ『パソコンおりおり草』を28回に亘り連載。
その他、山と溪谷社出版物各誌、朝日新聞出版物など各紙誌に執筆評論多数。