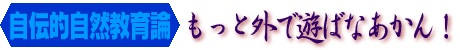
- 第2回 - 著者 高田 直樹
花を褒める、木を褒める
 つい先頃、二十数年ぶりに高校の教え子に会いました。彼は、ぼくの『なんで山登るねん』の愛読者でした。この本の内容を、書いたぼく自身も知らないような詳細にいたるまで、実に良く記憶しています。いつもトイレで読んでいるのだそうです。
つい先頃、二十数年ぶりに高校の教え子に会いました。彼は、ぼくの『なんで山登るねん』の愛読者でした。この本の内容を、書いたぼく自身も知らないような詳細にいたるまで、実に良く記憶しています。いつもトイレで読んでいるのだそうです。その彼が、「せんせ、ホームルームで話さはったあの話憶えたはります?」と訊ねました。たしかぼくが、「カラコルムヒマラヤの通はみぃんな死んでしまいよって、わし一人が生き残りみたいなもんや」そう話した時のことだったと思います。
あんなぁ、わしはな。山を歩いてて、奇麗な花が咲いてると、「きれぇな花咲かしたなぁ。偉いなぁ」ゆうて、褒めたるんや。ええ枝振りの木があったら、「かっこええ枝や。がんばったなあ」そういうたるんや。
ほしたらな、わしが雪の中で道を失った時に、その草やら木ぃやらが雪ノ下からわしに道をおしえてくれよるねん。
忘れてしまった感覚
正直いって、そんなことを話したことなど、まるで記憶になかったのです。でも彼はよく憶えていて、「ほれで、その話嫁はんにしたら、えらく感激しとるんですゎ。高校生の息子も、なんか分かるような気ぃするゆうてます」
その頃、ぼくの山登りは絶好調の時期だったようです。そして大変困難で危険な未踏峰に向かう直前でした。もしかしたら、そういう話を自分で信じようとしていたのかもしれません。
いやぁ、でもぼく自身、この話に結構感激したのです。感動しつつおおいに反省し、反省しつつ、ある不安も覚えていました。
自分は、そういうプリミティブな対自然感覚を、もうとっくの昔に、どこかに置き忘れてしまったのではなかろうか。
近郊の山々もスキーゲレンデも、もしかしたらぼくにとっては、単純に屋外のスポーツセンターとなってしまっているのではあるまいか。
自然の営みに言葉をかける
最近、この国はなんという緑豊かな国なんだろう、とそう思うことがよくあります。あの荒涼の極みのような場所から帰って来たばかりからかも知れません。
先月、ぼくはアフガニスタン難民援助の調査のためにパキスタン・アフガニスタンを回っていたのです。国境間近、トライバルエリアにあるシャルマンキャンプには、一万二千人の難民が岩山の裾の草木の全くない荒れ果てた平原に暮らしていました。
わが日本国は、家屋を一歩出ただけで、たとえそれがアスファルトジャングルの大都市であってさえ、草木を見ることが出来ます。
草木の持つ遺伝子DNAは、我々のものとさして変わらないのだそうです。
草木も、命を持つ地球上の仲間として生きている。そうであれば、ぼくたちは彼等の営みに対して言葉をかけてやらないといけないのではないか、そう思っているのです。
■バックナンバー
 もっと外で遊ばなあかん!(1)
もっと外で遊ばなあかん!(1) もっと外で遊ばなあかん!(2)
もっと外で遊ばなあかん!(2) もっと外で遊ばなあかん!(3)
もっと外で遊ばなあかん!(3) もっと外で遊ばなあかん!(終)
もっと外で遊ばなあかん!(終)■著者紹介
高田 直樹(たかだ なおき)
 1936年京都生まれ。京都府立大学卒。同大学山岳部OB。
1936年京都生まれ。京都府立大学卒。同大学山岳部OB。国際登山家。教育評論家。
大学卒業後、京都府立高等学校で化学の教鞭をとるかたわら、登山や教育についての執筆評論活動を行う。
主な登山活動は、厳冬期剣岳東大谷G1初登攀、積雪期前穂高岳屏風岩第1ルンゼ第2登など。
また、海外ではカラコルム、ネパール、旧ソ連コーカサス、中国など各地の未踏峰へ、隊長として数多くの登山隊の指揮をとる。中でも1979年のカラコルム、ラトックI峰(7,145m)の初登頂は世界的に知られている。
一方で、パソコンのデーターベース処理・開発の専門家としても著名。
現在、龍谷大学非常勤講師(教育情報処理)。
株式会社クリエイトジャパン取締役、Ez-Comsite France 社外取締役、
株式会社イージー・コムサイト 取締役。
著書
自伝的登山論『なんで山登るねん(正・続・続々)』(山と溪谷社)
体験的教育論 『いやいやまあまあ』(ミネルヴァ書房)
『入門 TURBO PASCAL プログラミング』(ソフトバンク社)
『dBaseIII PLUS ガイド』(ソフトバンク社)
『FRAMEWORKガイド』(ソフトバンク社)
『FRAMEWORKII EZ ガイド』(ソフトバンク社) など。
専門誌・雑誌他
1981年7月~9月京都新聞夕刊小説欄に92回の自伝的教育論『いやいやまあまあ』を連載。
1985年12月、NEC98ラップトップ機をネパール山中で初試用。『日経パソコン』誌の取材を受ける。ソフトバンク社『Oh!PC』1985年1月号特集・ボクの夢のパソコンに『ワープロが作家になる日』を執筆。1991年1月よりソフトバンク社『Oh! PC』誌上にエッセイ『パソコンおりおり草』を28回に亘り連載。
その他、山と溪谷社出版物各誌、朝日新聞出版物など各紙誌に執筆評論多数。