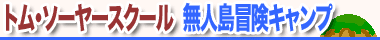
第2回 (財)安藤スポーツ・食文化振興財団
2日目
水汲みが日課
 なんとなく不安だったが、疲れていた子どもたちは、思い思いの場所に張ったテントでぐっすり眠ったようだ。朝、5時には目が覚めた。この頃になって、無人島にいるという実感が湧き出した。
なんとなく不安だったが、疲れていた子どもたちは、思い思いの場所に張ったテントでぐっすり眠ったようだ。朝、5時には目が覚めた。この頃になって、無人島にいるという実感が湧き出した。朝食の準備をするために、島の埠頭に用意された水タンクまで、水を汲みに下らなければならない。トイレもそこにしかないので、特に女の子は、何度となく200段もの階段の上り下りは、本当に大変だ。かなりつらい。
朝食は配給された、パン、ハム、チーズ、レタス、きゅうり、それにスープ。眠い目をこすりながら、火おこし作業から食事の準備が始まった。
24時間 時計、ライト、テントなし
 食事終えた子どもたちは、島の中央部にある草原に集まった。そこには、日時計が作られていた。キャンプディレクターから、『いま時間は8時です。これから24時間、この日時計が一周するまで、時計、電灯、テントなどはすべて回収します』と、宣告があった。あっけにとられた子どもたちを追い立てるように、カウンセラーがそれらの備品を回収しだした。
食事終えた子どもたちは、島の中央部にある草原に集まった。そこには、日時計が作られていた。キャンプディレクターから、『いま時間は8時です。これから24時間、この日時計が一周するまで、時計、電灯、テントなどはすべて回収します』と、宣告があった。あっけにとられた子どもたちを追い立てるように、カウンセラーがそれらの備品を回収しだした。これからのプログラムは、時計がないので、時間を想像しながら進めなくてはならない。特に決められたことはないが、魚釣り、島の探検、島にある洞窟の探検、野外遊びなどが、各グループに共通したプログラムとなった。これ以外に、今夜の野営地の決定や、食事の準備など、やらねばならないことは、結構多い。
魚釣りは、針と道糸となる凧ひもだけが支給された。竿は島に自生している竹を伐採して利用。錘は小石を工夫して、道糸を巻き込んで使うなど、子どもたちの工夫は、見ていて楽しい。
 子どもたちは、自家製の竿を担いで、少しは慣れてきた例の急な階段を下りて、埠頭の釣り場に向かった。このあたりの海はずいぶんきれいで、透明度も高い。そんなところで果たして釣れるのかと見ていると、数人の子どもたちが、ベラを釣上げた。歓声が上がった。
子どもたちは、自家製の竿を担いで、少しは慣れてきた例の急な階段を下りて、埠頭の釣り場に向かった。このあたりの海はずいぶんきれいで、透明度も高い。そんなところで果たして釣れるのかと見ていると、数人の子どもたちが、ベラを釣上げた。歓声が上がった。昼食は、小麦粉を練って作るチャパティ。中華なべの底を利用して、うまくチャパティができた。
 この無人島は、周囲がおよそ50mの断崖に囲まれているので、島の縁を歩くのは大変危険だ。足を滑らせれば、まず、助からない。そんな地形だということに、島の探検をすることで、ようやく子ども達にも、その危険度が理解できてきた。指導者が、いくら危険だと叫んでみても、なかなか体感的にはわからない。島の森にいる限り、小さな草原で遊んでいるだけでは、理解しようがないのだ。
この無人島は、周囲がおよそ50mの断崖に囲まれているので、島の縁を歩くのは大変危険だ。足を滑らせれば、まず、助からない。そんな地形だということに、島の探検をすることで、ようやく子ども達にも、その危険度が理解できてきた。指導者が、いくら危険だと叫んでみても、なかなか体感的にはわからない。島の森にいる限り、小さな草原で遊んでいるだけでは、理解しようがないのだ。つらい水汲みを何度も経験して、ツルでターザン遊びをして、埠頭で潮しぶきを浴びながら、なかなか釣れない釣りにチャレンジして、ようやく無人島で生活するのが、いかに大変かが分かりかけてきたようだ。
時折、本部の看護師のところに、鼻血や擦り傷の手当てを受けに来た子どもたちが、処置が終わった後、切なくなったのか、みんな同じように、泣きべそをかいた。
無人島生活2日目の夕刻になった。ヘッドランプやライトは、すべて没収されているので、早めに夕食と、野営場所を探さなければならない。テントがないので、蚊帳を吊るか、野天で眠るかも選択しなければならない。どうやら3グループが、森の中で、2グループが草原で野営をすることに決めたようだ。
 日が落ちだす頃、ようやく夕食の準備ができた。4度目の食事ともなると、火のおこし方も、それなりに慣れてきて、薪もうまくくべられるようになって、なんとなく後姿もさまになってきたようだ。
日が落ちだす頃、ようやく夕食の準備ができた。4度目の食事ともなると、火のおこし方も、それなりに慣れてきて、薪もうまくくべられるようになって、なんとなく後姿もさまになってきたようだ。今夜の夕食は、チキンラーメンと野菜。単になべに入れるだけか、炒めるのかは子ども達の好みだが、すきっ腹に『おいしいと!』唸って、平らげた。
主催 (財)安藤スポーツ・食文化振興財団
運営・指導 NPO法人国際自然大学校
文・写真 中村 達
運営・指導 NPO法人国際自然大学校
文・写真 中村 達
■バックナンバー
 トム・ソーヤースクール無人島キャンプ(1)
トム・ソーヤースクール無人島キャンプ(1) トム・ソーヤースクール無人島キャンプ(2)
トム・ソーヤースクール無人島キャンプ(2) トム・ソーヤースクール無人島キャンプ(3)
トム・ソーヤースクール無人島キャンプ(3)