


- 第1回 - 著者 奥村 彪生
(1)アウトドアで食べるということ
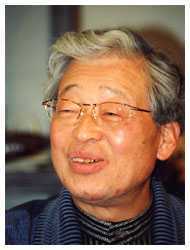 いつも家族と暮らしている家を離れて、野外で料理を作ることをアウトドアクッキングと呼ぶ。クッキングは火を使って食材を焼いたり、煮たり、ゆでたりすることを指す。したがって刺身はクッキングではない。そして野外での魚介や肉類の生食には危険が伴う。クッキングは食材を安全においしく食べるために、火を巧みに使う火工の技術である。それは頭脳の働き。
いつも家族と暮らしている家を離れて、野外で料理を作ることをアウトドアクッキングと呼ぶ。クッキングは火を使って食材を焼いたり、煮たり、ゆでたりすることを指す。したがって刺身はクッキングではない。そして野外での魚介や肉類の生食には危険が伴う。クッキングは食材を安全においしく食べるために、火を巧みに使う火工の技術である。それは頭脳の働き。科学的に考えながら食材を切ったり、片づけながら作業をし、限られた時間内に作り上げる。それはシステム。いかにおいしく作り、かつ食べる人たちを喜ばせるか。それは知的生産行動。
参加した全員で共同作業をし、語り合い、笑い合って開放的な気分でひとつの鍋、あるいはひとつの網の上の料理を分かち合って食べる。このことはコミュニケーションをとる重要な装置になっている。これは人間だけがもっている文化である。おいしさも増幅する。その結果心身が癒され、一体感が生じる。
また、風景もご馳走。自然の霊気をいただき、全身全霊を使って作業に打ちこもう。そのことによって、クライマックスのキャンプファイアーの感動が大きくなる。体を燃やす情熱が沸きあがる瞬間である。この霊気が明日からの勉学やクラブ活動に活かす礎となる。
(2)アウトドアクッキング事始め
| A. | 大切なことは場所選び。あまり遠方でなく、水場が良く、風景も優れているところが最適。川原で行う場合は天候の異変で増水するときもあるから、ラジオなどの天気予報で情報をキャッチしておく。施設が完備したキャンプ場が安心。 |
| B. | いつ、誰と行くか。季節によって同じ場所でも風景が変わるのと同様に、気温も変わる。その気温により、当たり前のことだが、服装も変えなくてはならない。そして誰と行くか。家族か友人か。車か徒歩かで装備やメニューが決まる。 |
| C. |
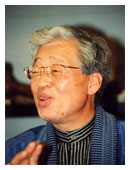 メニューは初心者でも作れる簡単クッキング。もっとも手軽なのはカレーライス。時間と材料の無駄をしないために、食材は手分けして大ざっぱにカットし、種類別に袋に入れる。肉類は塩をふり、カレー粉をまぶしておく。こうすると腐敗しにくい。現地で水とともに鍋に入れて煮るだけ。道具と作り方を分かりよく書いたマニュアルを前もって全員に配布して、役割分担を決めておく。 メニューは初心者でも作れる簡単クッキング。もっとも手軽なのはカレーライス。時間と材料の無駄をしないために、食材は手分けして大ざっぱにカットし、種類別に袋に入れる。肉類は塩をふり、カレー粉をまぶしておく。こうすると腐敗しにくい。現地で水とともに鍋に入れて煮るだけ。道具と作り方を分かりよく書いたマニュアルを前もって全員に配布して、役割分担を決めておく。せっかくのアウトドアクッキング、いつも家で食べるカレーライスとは違う味を。チョコレートを加えるだけで趣の変わったカレーに変身する。こんな遊び心が新しい発見や発明の礎になる。要するに創意と工夫が大切。 網焼きは炭火がおいしい。炭のおこし方をマスターする。肉や魚介はたれや塩、コショウで下味をつけておく。野菜はカットして油を薄く塗っておく。ごはん用の米は無洗米。柴を集めてはんごう炊き。柴の焚き方もマスターする。したがって調理道具は重装備でなく、ワンポット、ワングリルで。柴を焚いたり、炭をおこした場合は、火の後始末を完全にし、穴を掘った場合は復元を。 |
| D. | 栄養よりおいしさを大切に。アウトドアは体力を養うことにも一役をになうが、滞在期間が短いから心の栄養をとることが優先する。栄養のバランスを重要視すると食材の種類が増えるから、運搬が重装備にならないように、エネルギー源の米と、身体と心の働きに欠かせない蛋白源と野菜の組み合わせでよい。なにより大切なのは水。十分確保しておくことだ。人間は一日たりとも水は欠かせない。 |
■バックナンバー
 アウトドアクッキング事始め(1)
アウトドアクッキング事始め(1) アウトドアクッキング事始め(2)
アウトドアクッキング事始め(2) アウトドアクッキング事始め(3)
アウトドアクッキング事始め(3)■著者紹介
奥村 彪生(おくむら あやお)
昭和12年和歌山県生まれ。
伝承料理研究家。
日本各地の土地や家庭に伝承された食文化を見なおし、明日に生きる新しい伝統料理を研究する。平成6年、食生活文化賞を受賞。 著書に『日本の食べもの』『たのしくつくる健康野菜料理』(いずれも人文書院)
『おいしさ度あ・な・た流』(ぎょうせい)『日本料理秘伝集成』(同朋社)など多数。
また、テレビ番組などの出演も多い。
■関連情報
 神戸山手大学 人文学部環境文化学科
神戸山手大学 人文学部環境文化学科