


著者 川嶋 直
例えばあなたが
参加者を募集して
「自然体験活動の事業」を
企画して実施したいと思うなら…
参加者を募集して
「自然体験活動の事業」を
企画して実施したいと思うなら…
「自然体験活動」その企画と運営の方法(9のステップ)
●この9つのステップは以下を前提としています
・自然の中での体験を通して何らかの学びをえるための事業であること
・宿泊を伴う事業であること
・広く参加者を募集をして実施する事業であること
・子ども対象の事業であること
以上を前提としてその「企画」から「運営」そして「評価」までの9つのステップをおおまかに紹介しました。さらに詳しいことは以下のホームページを参考にしてください。ここにある情報の数十倍の情報があります。もしあなたの「自然体験活動」がこの前提と合わない場合(例えば:自然体験そのものが目的で、日帰りで、決まった会員対象で、大人たちを対象にした事業)である場合には、この9つのステップをあなた自身に合うようにアレンジしてお使いください。
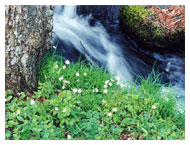 1)仕込み8割。まずは「企画」です
1)仕込み8割。まずは「企画」です企画とは、あなた(あるいは「あなたたち」以下同じ)の「思い」を「かたち」にすることです。どんな事業も企画がしっかりとしていなければ参加者を集めることもできませんし、様々な場面であなたを助けてくれる協力者も得られません。
●その事業の目的・意図を明確にしましょう
「楽しければそれで良いんでしょう?」いいえ、駄目です「楽しいだけじゃ許しません」。ちょっと大げさですが、あなたが「自然体験活動」を、参加者を募集して社会的な事業として実施しようとするのなら、「何のためにするのか?」抜きでは駄目であります。社会は「自然体験活動」に期待をしています。「そんな大それたつもりない」あなたは、どうぞお友達や家族だけでお楽しみください。もちろん、それだって立派な自然体験活動なのですから…。
●さあ、企画書を作りましょう
企画書は、あなたの考えていることを、皆にわかりやすく伝える「ラブレター」です。皆とは、その事業に参加してくれる人たちだけではなく、その事業に様々な形で協力してくれる全ての人々のことです。
「やりたいこと」「すべきこと」「出来ること」この3つをよく考えましょう。「やりたいこと」は、あなたの実現ししたいことそのものです。まずはその思いを文章に置き換えてみてください。「すべきこと」は、あなたと、あなたのグループ、あるいは別に主催者がいる場合にはその主催者の社会的な使命ですね。それと、人々にその事業が求められているのかも、ちょっと心を冷やして考えてみましょう。本当にその事業は、社会が時代が求めているものですか?「出来ること」は、まさにあなたの手に余ることがないかのチェックです。あるいは、逆にあなたの手の内にある「お宝」を見逃していやぁしませんか?
この3つのことをよ~くチェックしてから、「何のためにやるのか」を考えて、皆に支持される、企画を「企画書」に、表現してみましょう。
●企画の全段階で自然環境に負荷がかかっていないかをチェックしましょう
あなたたちの自然の中での活動や生活が、自然環境にどのような負荷を与えているのかのチェックは、プログラムの全ての段階で欠かせないことです。河原でバーベキューをして、その油汚れを川で洗うなどは論外ですが、自然体験活動を永く皆で楽むためにも、お借りしている自然のフィールドが、次の機会にも良い場として使い続けられるようにしましょう。自然体験は、素晴らしい自然環境があって初めて実現するのですから。
2)「受付」は、最初の参加者とのコンタクトです
受付は「問い合わせ」から「申し込み」までの一連の作業です。参加希望者はあなたの発したなんらかのメッセージ(呼びかけ)に答えて連絡をしてくれたのです。呼びかけが誤解無く伝わっているか、間違いない情報が参加希望者と主催者との間で共有できるかがポイントです。
●受付時に必要な資料を作りましょう
問い合わせが来た時に、正しく応えるための資料を手元に用意しておきましょう。希望者は電話・ファクス・eメールなど様々なメディアであなたに問い合わせて来ます。適切な情報を参加希望者に与えることが出来るように、また、申し込みの意思が確認できたら、必要な情報を間違いなく得られる手順を確認しておきましょう。
●可能であれば説明会を開催しましょう
子ども対象の数日間の宿泊プログラムの場合には、保護者に安心感を与え、このプログラムの意図を正確に伝え、装備や体調などの事前準備などについて、適切な情報を伝えるために事前説明会を開催しましょう。保護者はあなたたちの姿、言葉、立ち振る舞いを見て、安心したりあるいは心配になったりします。「そんなつもりじゃなかった」ということが後で起きないためにも、一度直接面会する機会は欲しいものです。ただし、参加者が広範囲に広がっていて事前に集まることが難しい場合には、事前説明会を開催するのと同じくらいのエネルギーを事前資料作りと、事前の電話などでの情報交換に傾けましょう。
3)結構抜けがちなのが「運営体制」作りです
誰が何についてどこまでの責任を持つのか。日本社会が比較的苦手なこうした取り決め(あるいは契約)について、出来るだけ企画段階できっちり決めておきましょう。ただ、こうした事業の経験が少ない団体の場合には、どんな役割が必要なのかもわからないでしょう。経験の長い団体の運営体制から学ぶことも良いでしょう。
●全体進行担当者やプログラムの進行担当者をきめましょう
主催者の代表者が必ずしも現場で直ちに判断できる位置に居ない場合もあります。自然の中は「変数」だらけです。天候異変、危険な生き物、災害などの自然条件によるものから、心の問題、喧嘩、いじめなど人的要因によるものまで「何がおこるか分からない」のが自然体験活動です。そうした突発的な出来事に瞬時に対応するためには、誰が判断できる人なのか予めはっきりと決めておく必要があります。ボランティアグループで主催する場合にはこの点、特に気をつけましょう。
 4)やっぱり「安全管理」を!
4)やっぱり「安全管理」を!前項にも少し触れましたが、自然の中は何があるかわかりません。だからこそドキドキ楽しいのです。しかし事故が起きてしまったら、それまでの楽しさは一気に吹き飛んでしまいます。身体と精神両方の安全管理を心がけましょう。
●子供たちの情報を事前に把握しましょう
食事や薬のアレルギーなど事前の保護者からの情報をちゃんと確認していますか。たとえ数時間の事業であったとしても、子どもたちの「いのち」を預かっているのです。保護者も「何もないだろうから」と、主催者から聞かれない限り、重要な情報を伝えない場合もあります。事前の情報のやりとりの中で、既往症やアレルギーなどについての情報は必ず確認しておきましょう。
●賠償保険、傷害保険に加入しましょう
どんなに注意していても事故は起きるものです。起きないように十分な注意を払うことと同じくらい、起きたときの対応をしっかりと計画しておきましょう。上記2つの保険は必ず入っておきましょう。詳しくは「自然体験活動 安全対策ハンドブック」などをご覧下さい。
5)宿泊プログラムなら「生活」も重要な部分です
「自然を体験させるのがこのプログラムの目的です」。結構ですが、数時間~数日間いっしょに過ごすのであれば、食事・睡眠・排泄などあたりまえの生活抜きに時間を過ごすことは出来ません。「ともに生活すること」も「自然体験活動」の重要な要素です。
●子供たちに生活自立の姿勢をもたせましょう
親元を離れて過ごす時間は、自立への格好のチャンスです。「自分のことは自分で」は言うに及ばす、「皆のために自分に何が出来るか」を考え行動する促しもしてみましょう。上記の安全管理のことを考えても「自分の身は自分で守る」というお約束は大切です。「人任せにしない場」であることを、最初に皆の了解事項にしておきましょう。
 6)周到な「実施の準備」を、分かりやすく伝える整理を…
6)周到な「実施の準備」を、分かりやすく伝える整理を…いよいよ最後の直前仕込みの段階です。スタッフが多ければ多いほど、事前に準備したことを共有することが大変になります。また、あなたのプログラムのねらいを実現するためにも、参加者用のハンドブックも作りましょう。
●スタッフのための運営マニュアルを作成しましょう
事前にスタッフだけのプログラム実施地での下見や打ち合わせをすることは最低必要条件です。万が一それが事前に実施できない場合にも、最低前日には現地入りして、現地の施設や自然環境を出来るだけ把握してもらいましょう。
そして、それを前提としてプログラムの、人間(スタッフ&参加者)、空間(施設&周辺地域)、時間(プログラムの進行)に関する情報をまとめた「スタッフのための運営マニュアル」を用意しましょう。プログラムは上にも記したように、必ずしも予定通りには行かないものですが、かと言って基本的なプログラムの組み立てをスタッフの間で了解(共有)しておかなければ、瞬時の変更も難しくなります。「周到な準備と柔軟な対応」プログラム実施上の極意です。
●参加者のためのハンドブックを作成しましょう
参加者のためのハンドブックは事前の準備のために1週間~数週間前に送るものと、当日会場で参加者に手渡すものとがあります。事前送付するものの役割は、プログラムへの期待を高めることと、しっかりした準備を促すことにあります。また、当日会場で手渡すハンドブックは、プログラムの効果を高めるために、期間中に考えたり感じたりしたことをメモしておく記録帳としての役割があります。こうした役割を担うハンドブックをロクブック(航海日誌)と呼ぶこともあります。
7)さあ、いよいよ本番です。「当日の運営」について…
いよいよ幕開けです。当日の朝は恐ろしく早く時間が過ぎてゆきます。出来るだけ前日までに「すべきこと」を済ませておきましょう。当日の会場集合直前には交通事情の変化や天候の具合、さらに参加者の健康状態の異変などによって、様々な「予定変更」の要因が生まれる時間帯でもあります。交通事情や天候などはしっかりと情報を把握しておきましょう。
●開会時には、しっかりとこの事業の目標を確認しましょう
開会のセレモニーはほどほどに…。プログラムの最初の時間帯は緊張と興奮で大切なことをが中々聞いてはもらえません。子どもたち対象のプログラムの場合には、出来るだけ早い時点で小さなグループに分かれて、担当のスタッフとの関係作りに努めましょう。そして、出来るだけ早い時点で今回のプログラムのねらいとするところ(目標)を、参加者と共有しておきましょう。事前の案内やあるいは説明会で再三説明した「つもり」でも、参加者は様々な期待を持って参加しています。最初の時間帯は「参加者の期待」と「主催者のねらい」とのチューニングの時です。
●必要な情報はその都度伝えるようにしましょう
前にも書きましたが、大切なことを開会式直後のオリエンテーションでつぎつぎと述べ伝えても実際には中々伝わらないものです。本当に伝えたい「大切な」ことはその直前に、間違いなく伝わったかを参加者の顔を確認しながら確認しましょう。特に安全や健康に関することは「ちゃんと言ったはずです」では済まされません。「伝える」ことと「伝わる」ことは別のことだと認識しましょう。
8)終わったぁ~カンパ~イ!じゃなくって、もうひと頑張り「評価会」です
事故も無く、参加者の子どもたちも皆笑顔で帰ってゆきました。子どもたちを見送るスタッフの目にはうっすらと涙が…。さあ、後片付けが済んだら「打ち上げ」でしょう。でもその前に、スタッフ全員の印象がフレッシュなうちに、この事業をきっちり「評価」しておきましょう。でもその前に、スタッフ全員の印象がフレッシュなうちに、浮かれた気持ちをちょっと静めて、事業を振り返りましょう。
●参加者の満足度、目標への達成度をはかって次のステップに…
評価は「次の事業の改善のための大切なステップ」です。「評価」という言葉は、人から査定されるとか評定されるという少し嫌なイメージがあるかもしれませんが、ここでは自ら進んで「自己評価」をしてみましょう。
良い評価のためには、具体的な情報が必要です。スタッフがその事業をどう捕らえたかも大切ですが、参加者がどうとらえたのかという情報を集めましょう。通常「アンケート」という手法を取りますが、特に子どもたちのプログラムの場合には、文章を書いてもらうことはあまり期待できません。最後の評価会を少し意識して、子どもたちの様子を出来るだけ客観的に観察して、評価のためのデータを集めておきましょう。
また、評価は「目標への達成度を計る」作業でもあります。つまり、最初に具体的な目標を皆で定めておかないと、それを成果とを比較して評価することが出来ません。「事業の終了時点でどうなっていたいのか?」を、企画段階で可能な限り定めておきましょう。
そして評価会では、次への改善提案を必ず残すようにしましょう。次の企画はこの改善提案を読み直すところから始まるのです。
 9)まだまだ終わっていません「実施後の対応」を…
9)まだまだ終わっていません「実施後の対応」を…アフターケアは自然体験活動の効果をより深いものにします。非日常の体験であったあなたの自然体験活動から、日常の学校や家庭生活に帰って、子どもたちの気持ちがそちらに向かうことは当然です。ただ、「あれは特別な体験だった」という記憶だけで、果たしてあなたの「思い」は「かたち」になったのでしょうか?
●事後のコミュニケーションをもちましょう
事後のコミュニケーショの持ち方にはいろいろな方法があります。参加者側からの情報を集める方法としては、子どもたちと保護者に対して、数週間後にアンケートを取る方法もあります。またその時期にあわせて、主催者から参加者にプログラム中の写真や何かプログラムの成果物を送るという方法もあります。また、プログラム期間中に「○ケ月後の自分への手紙」を書いてもらい、それをその期日に送付するという方法もあります。
いずれにしても、あなたの「思い」を「かたち」にするために必要な(可能な)範囲のアフターケアを計画してみましょう。
■なおこの原稿は「平成13年度文部科学省委嘱事業 自然体験活動 企画・運営ハンドブック」をベースに川嶋直が加筆・再構成しました。
ハンドブック編集&執筆メンバー
川北秀人 河崎悦子 小林毅 佐藤初雄 角南明子 西村仁志 増田直広 藁谷豊【アイウエオ順、敬称略】
■バックナンバー
 「自然体験活動」その企画と運営の方法
「自然体験活動」その企画と運営の方法 自然体験活動の企画の極意!!
自然体験活動の企画の極意!!■著者紹介
 川嶋 直(かわしま ただし)
川嶋 直(かわしま ただし)1953年東京生まれ
財団法人キープ協会常務理事(環境教育事業担当)
社団法人日本環境教育フォーラム理事
NPO法人自然体験活動推進協議会理事
1980年、山梨県清里、八ヶ岳の麓にある財団法人キープ協会に就職。1984年から環境 教育事業を担当。森の中での様々な自然体験プログラムを通して、この素晴らしい自 然環境のために働くことが出来る人を育てることを目指して、様々な仕事をしてい る。現在約20名のスタッフと共に、主に大人を対象に年間20回の宿泊型のプログラム と、80回の受託プログラムを清里を中心に全国各地で実施している。インタープリ ターとは、通常、通訳という意味だが、米国の国立公園などで「自然と人間との橋渡 し役」という専門職をこのように呼んでいたことから、最近わが国でもこうした呼称 を使うようになってきた。
著書:「就職先は森の中~インタープリターという仕事」(1998年小学館)
共著:「日本型環境教育の提案」(1992年小学館)「野外教育入門」(2001年小学館)
監訳:「インタープリテーション入門」(1994年小学館)
■関連情報
 「自然体験活動 企画・運営ハンドブック」(Adobe Acrobat Readerが必要です)
「自然体験活動 企画・運営ハンドブック」(Adobe Acrobat Readerが必要です) 財団法人キープ協会 (環境教育事業部)
財団法人キープ協会 (環境教育事業部) 国立オリンピック記念青少年総合センター
国立オリンピック記念青少年総合センター