


著者 佐藤 初雄
自然体験活動における安全管理について、リスクへの対処(危険予知~危険回避)を5つのポイントに絞り考察します。
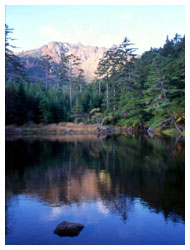 1.安全管理の考え方
1.安全管理の考え方(1)想定できるだけの危険を予知し、そのための対策を徹底的に講じること。
(2)万が一の時を想定して対策を講じるとともに、スタッフに対する教育を徹底して行うこと。
(3)参加者には自分のみ身の安全は自分で守ることを徹底させること。ただし、参加者が未成年者である場合、保護者に活動の主旨、内容といったものをきちんと伝えたうえで参加してもらうこと。(万が一の時に保護者の責任も問われます。)
以上3点が基本です。
2.危険因子の分類
私たちが行う活動の多くは、非日常的な自然環境の中で行われるものです。従って日常的に予想される危険とはかなり異なります。指導者はまずこの点をきちんと認識しなければならないでしょう。
(1)自然環境の危険
ア)気象によるもの大雨、吹雪、強風、台風、落雷など。
イ)地震によるもの山崩れ、津波、火災など。
ウ)人体に影響を及ぼす危険な動植物毒蛇、ハチ、ケムシ、ウルシ等。
エ)その他洪水、雪崩、火災など。
(2)生物的な危険
ア)病気伝染性病原体や寄生性病原による疾病。食中毒、その他の疾病。
イ)怪我すべる、転ぶ、ぶつかる、落ちる等による怪我。
(3)社会性、文化性、人為的な危険
ア)人間関係によるもの人間関係のこじれ等による精神、身体的な危険。
イ)文明の利器によるもの刃物や火、あるいは道具の扱い方の失敗による怪我。
交通事故。
ウ)主催側、指導側の過失による危険無理な計画、未熟な指導者による事故等。
この他にもまだまだあるとは思いますが、少なくても前述したようなポイントで活動を実施する日程、場所、内容、対象者の状況等を予想して、どのような危険があるのかを確認することが必要です。
とにかく、想定できるかぎりのあらゆる危険を予測することが最初の取組みです。そしてそれらの危険をいかに回避するかの対策を立てることが重要です。
危険予知能力と危険回避行動こそが安全管理の全てであると言っても過言ではありません。しかし、これらの能力は決して書物を読んだから身に付くというものではありません。実践という経験を積むことが大変重要です。
3.事前のリスクチェック
計画段階でのリスクチェック
この計画の段階こそが事業の成否だけでなく安否についてもカギを握っていると言っても過言ではありません。それでは以下に挙げるポイントについて述べていきましょう。
(1)テーマの設定
どのようなタイトルをつけ、どのような目的で事業を行なうのかを明確にします。
(2)対象者の設定
この事業は誰を対象にして何名ぐらいで実施するのかを明確にします。
(3)活動プログラムの決定
どのような活動プログラムを実施するかを決定します。
(4)組織の決定
事業を安全に成功させるためには、どのような役割が必要で、どのような
組織にするのかを明確にします。
(5)指導者の決定及び、指導者資格基準
事業を安全に成功させられる能力を持っている指導者かどうかを見極め、
指導者を決定します。
(6)場所・施設の決定
テーマや活動プログラムが実施可能な場所や施設を選ぶことは当然ですが、
安全面に対するチェックも確認した上で決定します。
(7)用具・持ち物の決定
活動を行なうために必要な用具や個人の持ち物を決定します。
(8)輸送手段の決定
安全性の高い交通手段であるか否かを確認した上で決定します。
(9)保険の加入
活動の内容や予算に応じて適正な保険に加入します。
以上のようなポイントに十分配慮した上で計画を立てることが必要です。とにかく安全上無理がないかどうかを念頭にいれた計画づくりが重要です。
4.指導者や責任者が注意すべき安全管理のポイント
こうしたケガや事故がなぜ起きるのでしょうか。また、指導者はどのようなポイントに注意すればいいのでしょうか。少し考えてみたいと思います。自然体験活動は、大きく分けて3つの要素によって構成されています。
(1)事故のメカニズム
不安全な状態×不安全な行為=事故発生(約8割)と言われています。つまり、事故発生率を下げるには2つの状態と行為をよく理解し、双方の危険値を低くすることです。
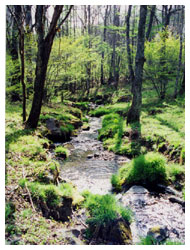 ア)不安全な状態(外的要因)
ア)不安全な状態(外的要因)・環境要因:自然環境(たとえば気象の不良)
・活動環境(場の不良)
・物的要因:施設、道具、服装の不備
イ)不安全な行為(人的要因)
・知らない
安全に関する理解と認識が不足している。
安全に対する知識が不足している。
危険に対する感受性が不足している。
・やれない
能力が不十分でやれない
能力はあるが、フルに発揮できない。
・やらない
知識や能力が合ってもやらない。
規律に弛緩があるためやらない。
教育指導が低調になっているためやらない。
(2)事故を未然に防ぐためのトレーニング
指導者や責任者は以下のことについて熟知し、トレーニングをする必要があります。
ア)対処法としての応急処置(ファーストエイド)
心臓、肺の蘇生法(CPR)、出血、骨折等の手当ての手法。
イ)事故を未然に防ぐための危険予知トレーニング
危険予知トレーニングは、参加者全員がこれから行われる活動の
イラストを見ながら、どんな危険があるかを発見し、その危険を
いかに回避するかという対策を話し合い、意識化し、行動するた
めの方針を明確化するプログラムです。このプログラムを通して
事故のメカニズムの理解と危険予知トレーニングを行ないます。
ウ)トータルリスクマネジメント
保険への加入
非常時体制の確立
バックアップ体制(事務・広報的役割をできる人)の確立など。
以上のようなことが安全管理のポイントになります。これだけが正しい、又は、これだけ行えば安全対策は大丈夫ということではありませんので注意してください。
5.調査報告書からみるケガの状況
ところで、実際にはどのような事故がいつ、どんな場面で起きているのでしょうか。2つの調査報告から見てみましょう。
まずは、国立オリンピック記念青少年総合センターが1998年度夏休みに小中学生を対象に4泊5日以上の自然体験事業(主としてキャンプ)を実施した66青少年教育施設の参加者2928人に対しての調査結果です。
(1)男女別、プログラム別のケガの発生状況について見た場合
女子に比べて男子のケガの発生率が高いのは、「自由時間」と「川遊び・海遊びやカッター・いかだ・ボート」で、逆に男子に比べて女子のケガの発生率の高いプログラムは、「登山・ハイキング・岩のぼり」と「野外炊飯(調理中)」でした。
(2)傾向と対策
男子の自由時間におけるケガは、やや羽目をはずし、ふざけ半分の行動の中で生じている割合が大きく、男子の川遊びやカッター等では、「転んだ・つまづいた」がやや多いほか、「川底の石や貝殻、フジツボを踏んだ」「釣り針が刺さった」などが目立ちます。川遊び等でのケガは男子のケガの一般的傾向と呼応していると考えられます。
次に、ユースサービス大阪の畠中彬氏が近畿の野外活動センターやキャンプ場、約120施設を対象に1997年から2001年までの5年間の事故比較事例を整理分析された調査では、
(1)転倒、転落、衝突による打撲、骨折、切傷が毎年多い
転倒はグラウンドや体育館で走り回っている時が多いが、ハイキングやウォークラリーで山道を歩いている時や、スリッパが滑った、川遊びでつまずいた等、走っているとき以外の転倒も増えてきました。
(2)顔面、頭部のケガが増加傾向
キャンプファイヤーの火の粉が目に入って、目の玉をヤケドしました。また最近は虫よけスプレーがキャンプ場に持ち込まれるようになり、このスプレーの噴射液が目に入る事故も徐々に増えてきています。
(3)包丁やナタ等、刃物による切傷が多い
キャンプでは、野外炊さんやハンドクラフト等で、包丁、ナタ、ナイフ等刃物を使うことが多い、そのためこれら刃物による切り傷や裂傷が毎年後を絶たちません。
(4)ガスボンベ、着火剤等の使用に伴う事故の増加
青少年や大人が使うガスコンロやガソリンコンロ、着火剤等の新しい便利商品が、新しい事故の原因となってきました。
(5)キャンプ場を脅かすスズメバチ
かつてはキャンプ場でこわい生き物はマムシでした。しかし最近はマムシよりスズメバチによる事故の方がキャンプ場では多発しています。
以上のように、自然体験活動中におけるケガの状況についての調査報告書(一部のデータではあるが)を見ると、どのような活動時でどんなケガをするのかといった傾向がわかるようになりました。
こうした情報を頭に入れて活動することで危険予知対策の一つになりますので、ぜひ積極的に情報を入手したいものです。
出典 指導者のための安全対策読本
自然体験活動安全対策ハンドブック
■バックナンバー
 自然体験活動のリスクマネジメント
自然体験活動のリスクマネジメント 今の子どもたちに浴びるほどの自然体験活動を
今の子どもたちに浴びるほどの自然体験活動を■著者紹介
 佐藤 初雄(さとう はつお)
佐藤 初雄(さとう はつお)1956年東京生まれ。国際自然大学校 代表。
(社)日本環境教育フォーラム 理事、自然体験活動推進協議会副代表理事、日本野外教育学会理事、 日本アウトドアネットワーク事務局長などを務める。日本の野外活動の実践的指導の第一人者として知られる。
共著に「日本型環境教育の提案」(小学館)「子どもと環境教育」(東海大出版)「野外教育入門」(小学館)などのほか、 監訳に「キャンプマネージメントの基礎」(杏林書院)などがある。
■関連情報
 国際自然大学校
国際自然大学校