


- 第487回 - 筆者 中村 達
『登山、ハイキング、トレッキング 言葉の意味と違い』
登山、山登り、山歩き、ハイキング、トレッキングなど、アクティビティの単語や言葉がいろいろあって、少し混乱気味に感じている。国内の無雪期の山では、どれもこれもそれなりに意味は、理解はできる。
一般的に登山人口という言葉は、通念としてなんとなくわかるが、統計として厳密に分類するとなると少し違ってくる。
日本アルプスの山々を登るのは、無雪期は決して難しくはない。ある程度の体力と装備、食料などがあれば登ることが可能だ。かつては、歴史的にも生活文化の中に浸透していたし、近年では学校の集団登山として、その対象になっていた山も多い。
しかし、冬は決して簡単ではない。豪雪と急峻で入り組んだ地形は、雪崩が頻発して非常に危険で、登攀にはトレーニングとしっかりした準備が必要だ。そのため、季節を無視して、一括りに登山と言うには無理がある。
米国のアウトドア人口統計は、Backpacking, Hiking, Climbingの3つに分類されていて、トレッキングはない。ClimbingにはTraditional, Ice, Mountaineeringという注釈が入っている。ちなみにこのClimbing人口は、およそ160万人だ。これに対して、Hiking人口は約3500万人で、国民的なアウトドアアクティビティになっていることがわかる。Backpackingは徒歩旅行であるが、日本ではまだ馴染みにくいように思う。だからあまり使われていないようだ。
日本国内の登山人口はおよそ1,000万人とされている。しかし、この調査を行った機関にたずねてみると、登山の定義はしていないということだった。正確な統計をとるには、言葉の定義が必要だと言ってはみたが、はたしてどうなったか・・・。

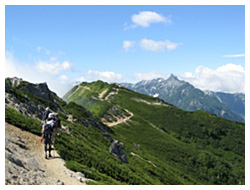
そこで必要とされるのが、外国語でのインタープリテーションだ。ガイドはもちろん、外国語版の地図やガイドブックも、必要条件になってくる。それには、登山、山歩き、ハイキング、トレッキングなどといった言葉や単語の統一化がいると思う。
ネットで言葉の使われ方、使い方を調べてみた。すると、的確な記述があったので、一部を引用する。
『アメリカで10倍うまく立ち回る方法』 Maki-K
「英語のhikingは登山・トレッキング・散歩、すべてをカバーするアクティビティです。頂上目指して山を登るのもhiking。トレイルを長時間歩くのもハイキング。小さい子供と一緒に池の周りを歩くのもhiking。とにかく自然の中を自分の足で歩くのがhikingです。もちろん英語でもmountain climbing(登山)やtrekking(トレッキング)という単語はあります。でも一般的に日本語で言う登山・トレッキングに該当する単語はhikingです。」
この意見は米国の状況をさしているのだろうが、ヨーロッパでもほぼ同じだと思う。ただ、ネパールや他のアジア地域では、トレッキングと言っているようだ。だからどうだというわけではないが、これからはインバウンドに対応した英語訳がいる。その時、例えばロングトレイルでのアクティビティをHikingとするか、Trekkingと訳すのか、しっかりした論議が必要だろう。
※画像はイメージです。
(次回へつづく)
■バックナンバー
■筆者紹介
中村 達(なかむら とおる)
京都生まれ。アウトドアジャーナリスト・プロデューサー
安藤百福センター副センター長、特定非営利活動法人日本ロングトレイル協会代表理事、全国「山の日」運営委員、公益財団法人日本山岳ガイド協会特別委員、国際自然環境アウトドア専門学校顧問など。
生活に密着したネーチャーライフを提案している。著書に「アウトドアズマーケティングの歩き方」「アウトドアビジネスへの提言」「アウトドアズがライフスタイルになる日」など。『歩く』3部作(東映ビデオ)総監修。カラコルム、ネパール、ニュージランド、ヨーロッパアルプスなど海外登山・ハイキング多数。日本山岳会会員