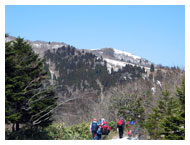- 第69回 - 著者 中村 達
『比良山索道の廃業』
びわ湖の西岸にそって、南北に連なる山域を比良山系という。標高1000mそこそこの低山だが、急峻な渓谷と、ブナの原生林などが残る趣のある山域である。また、南北に2ヶ所のスキー場があり、京阪神に近いということもあって、多くのスキーヤーでにぎわった。
そのスキー場のひとつ、比良山スキー場が閉鎖になった。そして、この3月31日で、山麓からスキー場に上がるリフトとロープウェイも、43年の歴史を閉じることとなった。
最盛期にはスキー場への登るだけで、何時間ものリフト待ちをしなければならないほどで、1983年には10万人以上の利用者があった。それが最近では半数近くに減少し、累積赤字が15億円にも達して、ついに廃業に追い込まれた。存続を求める署名運動もあったが、実らなかった。
このリフトとロープウェイは、スキーだけでなく最高峰の武奈が岳に登る登山客やハイカーにとって、大変便利なものだった。私も幾度となく利用させていただいた。特に、登山に慣れていない初心者や、高齢者と同行するときは便利だった。登りだけで2時間は短縮できた。リフトの基点が標高330m。ロープウェイに乗り継ぐシャカ岳駅が750mで、終点の山上駅が967mだから、その差約630mを索道が運んでくれた。このリフトとロープウェイのおかげで、遭難せずに助かった人も、実数は不明だが、さぞ多いことだと想像する。
|


|
3月最後の日曜日、リフトとロープウェイに乗り、武奈が岳に登った。別れを惜しむように、大勢の登山者がリフト待ちをしていた。長いリフトとロープウェイを乗り継いで、山上駅に着いた。ここから武奈が岳までは、ブナの森を1時間30分ほど登れば、すこぶる展望のいい頂上に立つことができる。
この日は快晴だった。残雪が1mほどあったが、直線的に歩けるので、予想外に早く頂上についた。南は大和葛城山系、東は伊吹山から加賀の白山、遠くに乗鞍岳、北から西にかけては日本海につながる、残雪の北山が一望できた。足元にはびわ湖が広がり、そのはるか向こうに、鈴鹿の山並みが見えた。
頂上は登山者で溢れかえっていた。中高年登山者が中心だったが、ちらほらとファミー登山者もいて、なんだかホッとした気持ちになった。
|
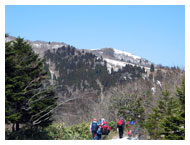
山上駅から武奈が岳

武奈が岳(1,214m)山頂
|
索道が廃止され、このあとは環境保全のため、全てが撤去されると聞いた。営業されないスキー場のレストハウスも無くなる。登山シーズンになると、この八雲が原の草地には、テント村になった。これからは、そんな風景も少なくなるのだろうか。
登山者やハイカーが減ると、自然環境へのインパクトは少なくなり、ブナの原生林や八雲が原湿原も、保全されるのだろうが、管理者がいなくなることで、保たれていた人と自然と人との絶妙なバランスが崩れるのではないかと思う。
こんな疑問を索道のスタッフに聞いてみると『レストハウスが撤去されることで、浄化設備のあった水洗トイレは、使用できなくなります。どうなるんでしょうね』と寂しげな答えが返ってきた。
|

廃業になった比良山スキー場
|
年間数万人が訪れるこの山域で、安全のための登山道の整備や道標の管理などは、だれが責任をもって行なうのだろうか。都市近郊のフィールドだけに、これから様々な問題が浮上してくるに違いない。もちろん、ここで働いていた大勢の人達の再雇用も、気がかりだった。
リフト乗り場にある小さな売店の主人が、要望があるので、土日曜日だけは営業し続けますという言葉に気持ちが和らいだ。
(次回へつづく)
■バックナンバー
■著者紹介
中村 達(なかむら とおる)
1949年京都生まれ。アウトドアプロデューサー・コンセプター。
通産省アウトドアライフデザイン研究会主査、同省アウトドアフェスタ実施検討委員などを歴任。東京アウトドアズフェスティバル総合プロデューサー。
生活に密着したネーチャーライフを提案している。著書に「アウトドアズマーケティングの歩き方」「アウトドアビジネスへの提言」「アウトドアズがライフスタイルになる日」など。『歩く』3部作(東映ビデオ)総監修。カラコルムラットクI、II峰登山隊に参加。
|