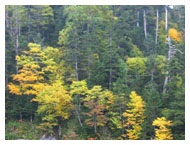- 第17回 - 著者 中村 達
「乗鞍スカイライン乗用車乗り入れは、『Last Year!』」
自動車で行ける国内最標高は乗鞍岳だ。乗鞍スカイラインを利用すれば、乗鞍岳山頂直下の畳平(約2,700m)まで、自家用車で登ることが出来る。何の苦労もなく、3,000m近くの高度が体験でき、晴れていれば眺望もすこぶるいいので、人気がある。旅程に上高地や新穂高温泉、高山などを組み合わすと、日本でも屈指の観光コースにもなる。
だが、乗鞍スカイラインは、今年の10月31日をもって、自家用車の通行が禁止されることになっている。バイクも通行できない。許可されるのは、麓からのシャトルバスや観光バス、山小屋やコロナ観測所、その他関係者の車両に限られる。
通行禁止の理由は、いくつかあるが最大の理由は、自然環境の保護だ。この乗鞍スカイラインは、今年で30年間の償還期限が終了する。つまり、来年以降は本来なら無料化するわけだが、そうなればさらに利用者が増え、渋滞はいっそうひどくなって、どうしようもない混乱が予想される。車が増えれば、排気ガスによる環境悪化は、いっそうひどくなる。それを避けるためには、乗用車の通行禁止というのが、最善の策だったようだ。
|

乗鞍スカイライン |
この乗鞍スカイラインは、夏休みや秋の紅葉シーズンともなると、畳平の駐車場に入れない車で、大混乱がおこる。何年か前の夏、私も畳平より遥か下で、ものすごい渋滞に巻き込まれ、登るのを断念して引き返したことがあった。何千台もの車が、排気ガスを撒き散らせば、環境にいいわけはない。ちなみに昨年は、157,208台の自動車(バス、バイク含む)が訪れた。
そして、今年は自家用車通行の最後とあって、駆け込みの観光客や登山者が殺到している。8月末でなんと209,208台もの自動車が、乗鞍スカイラインを利用した。紅葉シーズンにはさらに利用者は増えるだろうから、開通以来最高の台数になるだろう。
|

畳平 |
さて、そんなラストチャンスだからと、私も急遽乗鞍岳に登って来た。すでに2,000mあたりでは紅葉が始まっていた。畳平付近ではナナカマドの葉は落ち、赤い実だけが残っていた。
駐車場は平日にもかかわらず、渋滞が起こっていた。今年はずーっと満車状態だそうだ。正午をまわっていたので、わずかな待ち時間だけで、なんとか車を止めることが出来た。
ここから最高峰の剣が峰(3,026m)までは、火山礫の登山道を1時間半ほど登ればいい。ただ、いきなり3,000mの高度だから、山になれていない人はちょっと苦しいかも。
この日、天候は良くなかったが、ガスの切れ間から穂高連峰や、槍ヶ岳が薄っすらと見えた。
|
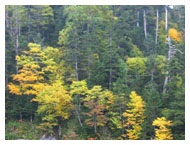
紅葉 |
乗鞍を訪れる大半の観光客は、せいぜい駐車場周辺部の散策をするだけで、その後は、土産物を買って、次の目的地に移動するそうだ。もっとも、駐車場には数多くの土産物店はあるものの、案内所はバスセンターに、目立たない小さな窓口があるだけで、ビジターセンターは見かけなかった。ビジターセンターがあると思って探してはみたが、見つけることが出来ず諦めた。
自然環境の保護・保全は、ルールでありマナーでもある。しかし、残念ながら現状では、教育から入らねばならない。そのためには、乗鞍岳のような自然環境には、しっかりしたビジターセンターが必要だと思う。観光バスがエンジンをかけっぱなしで、運転手が雑談に興じていた。バスガイドのオネエサンが、「上高地はここと違って盆地です」などと、トンチンカンな説明をお客にしていたのを聞いた。
土産物店やレストランもいいが、まず、ビジターセンターがなく、インフォメーションセンターの存在も目に付かないというのは、バランスを欠いていると思った。
|

乗鞍岳山頂 |
私も利用したので、偉そうなことは決して言えないが、やはり、このスカイラインは造ってはいけないものだった。そう感じた。
料金所の係員が「ことしは、LAST YEAR!」と言った英語が、なぜかいつまでも耳に残った、最後の乗鞍スカイラインだった。
|

山頂から |
(次回へつづく)
■バックナンバー
■著者紹介
中村 達(なかむら とおる)
1949年京都生まれ。アウトドアプロデューサー・コンセプター。
通産省アウトドアライフデザイン研究会主査、同省アウトドアフェスタ実施検討委員などを歴任。東京アウトドアズフェスティバル総合プロデューサー。
生活に密着したネーチャーライフを提案している。著書に「アウトドアズマーケティングの歩き方」「アウトドアビジネスへの提言」「アウトドアズがライフスタイルになる日」など。『歩く』3部作(東映ビデオ)総監修。カラコルムラットクI、II峰登山隊に参加。
|