


- 第279回 - 筆者 中村 達
『トムラウシ山遭難事故調査報告書を読んで』
 昨年7月、北海道の大雪山系のトムラウシ山で、未曾有の大量遭難事故が発生した。その遭難事故報告書を読んだ。この事故が注目されたのは、8名もの犠牲者を出しただけでなく、その登山自体がいわゆる「ツアー登山」だったからである。
昨年7月、北海道の大雪山系のトムラウシ山で、未曾有の大量遭難事故が発生した。その遭難事故報告書を読んだ。この事故が注目されたのは、8名もの犠牲者を出しただけでなく、その登山自体がいわゆる「ツアー登山」だったからである。ツアー登山は旅行代理店などが主催し、一般募集をおこなう。1980年ごろから始まった中高年の登山ブームで、1990年あたりから、このツアー登山は人気が上昇した。いまや、登山専門の旅行社だけでなく、多くの旅行代理店がツアー登山を企画している。
ツアー登山とはわかりやすく言えば、営業登山である。基本的にはお金さえ出せば、好きな山、登りたい山に連れて行ってもらえる。ビギナーや、中高年登山者にとってはありがたい存在であるのは確かだ。
報告書は旅行代理店の企業としての利益追求と、安全登山の狭間でどのよう行動がとられたのかを、ガイドや参加者の証言や現地調査などを行いながら、事故の原因を究明している。ガイドや参加者の証言はリアルで、読みすすめるにつれ戦慄を覚えた。
8名の死因は低体温症とされている。低体温症とは疲労して、体温が下がって死に至る症状のことだ。報告書が夏に低体温症で8名(同じときに大雪山系では10名)もの 登山者が亡くなったのは「日本の登山史上初めてであり、世界でも類をみない」と指摘しているほど、この遭難は異常な事態であった。
そして、事故原因の第一義は、リーダー、ガイド・スタッフの判断ミスによる「気象遭難」であるとしている。
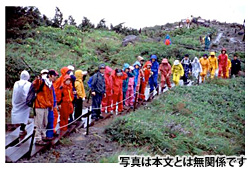 国内では、2008年度に1631件の遭難事故が発生し、死者、行方不明者は281人で過去の最多記録を更新した。遭難者は50歳以上の中高年者が大半である。
国内では、2008年度に1631件の遭難事故が発生し、死者、行方不明者は281人で過去の最多記録を更新した。遭難者は50歳以上の中高年者が大半である。戦後、モノのない厳しい時代を生き、高度成長期には企業戦士として働き、あるいは子育てに追われ、中高年齢の域に達してようやく手に入れた自由時間を、さほどのトレーニングなしでも楽しめるのは、誰にでも出来る「歩く」である。何よりも歩くことは健康にいい。そんな理由から、山を歩き始めた中高年者は多い。
68%が山岳丘陵地帯であるこの国の地勢は、山という格好の遊び場を中高年登山者に提供し、日本百名山は持続可能な最良の目標になった。
が、そのようなムーブメントの背景には次のような課題や問題があると、報告書は指摘している。
要約すると(1)若者の山離れと、若い登山者の減少。(2)学校山岳部、社会人山岳会などの衰退による教育システムの劣化。(3)登山をウォーキングなどと同列に考えた危険意識の欠如。(4)登山の勉強不足や学習機会の減少(5)旅行の延長感覚で企画するツアーの台頭(6)ツアーガイドの人材不足(7)旅行ビジネスと旅行気分の参加者の狭間でプレッシャーがかかるガイド。
つまり、若者の山離れによって、登山を支える学校や社会の教育システムが劣化しているところに、トレーニングや経験不足の中高年登山者が増加し、山岳ツアーの未成熟さも中高年登山者の遭難事故の多発につながっている、と推察される。
登山は常に危険が付きまとう。だから、危険を予測し、食料、装備などさまざまな準備をする。体力をつけるためにトレーニングをおこなう。そんな結果、苦労して登った山頂では、都会では決して得られない達成感がある。
子どもたち、若者たちにとって登山は、我慢することも学ぶ。さらに、キャンプだけでは得ることが出来ない、仲間との連帯感や協調性の重要さを体験することだろう。
若者たちの登山離れも、マクロ的視点で見ればトムラウシ山遭難事故の遠因であると思うのは私だけであろうか。
(次回へつづく)
■バックナンバー
■筆者紹介
中村 達(なかむら とおる)
1949年京都生まれ。アウトドアジャーナリスト/プロデューサー
NPO法人自然体験活動推進協議会理事、国際自然環境アウトドア専門学校顧問、日本アウトドアジャーナリスト協会代表理事、NPO法人アウトドアライフデザイン開発機構副代表理事、東京アウトドアズフェスティバル総合プロデューサーなど。
生活に密着したネーチャーライフを提案している。著書に「アウトドアズマーケティングの歩き方」「アウトドアビジネスへの提言」「アウトドアズがライフスタイルになる日」など。『歩く』3部作(東映ビデオ)総監修。カラコルムラットクI、II峰登山隊に参加。日本山岳会会員。