


- 第248回 - 筆者 中村 達
『佐渡の山を歩く』
佐渡出身の知人に誘われて、連休に佐渡島の山を歩いてきた。
佐渡島に標高1,000m級の山があると知っている人は、それほど多くないように思う。私も佐渡島へ出かける直前まで、実のところ佐渡島についてまったく知識がなかった。大河ドラマ「天地人」で、このあと佐渡島が舞台となるシーンがあるそうだが、これまではせいぜい金山、トキの人工繁殖程度しか思い浮かばなかった。それではいけないと、アクセスやトレッキングのルートなどを調べていくうちに、恥ずかしながらようやく島の全容が理解できた。
佐渡市のH.P.などによると、面積は855.25㎡と東京23区の1.4倍で、東西32.7km、南北59.5km。海岸線は280.4kmだそうだ。人口は67,000人。そして、大佐渡山脈にある最高峰の金北山は標高1,172m。
佐渡島のトレッキング用の地図(http://www.ryotsu.sado.jp/trek/01_root/index.html)やリーフレットなどは、観光協会から送ってもらい、ようやく予備知識も少しはついた。
新潟港からフェリーに乗船し、島が近づくにつれ、残雪の山々が見えてきた。何か不思議な感じだ。実際に見ると山容は予想より大きく高い。佐渡では知人の実家にお世話になった。
4月から5月にかけて佐渡は、花の山として知る人ぞ知るらしく、山野草を見に訪れる人たちも多いと聞いた。

私たちは青粘(アオネバ)登山口からマトネ(937.5m)を経由して、真砂の峰、天狗の休み場などを通り、自衛隊のレーダーがある金北山を登り、終着点の白雲台まで8時間ほどのトレッキングルートを歩いた。
歩き出すとすぐに「シラネアオイ!」と誰かが声をあげた。そこからはコース沿いにシラネアオイの群生が続いていた。ヒトリシズカ、ニリンソウ、ユキワリソウなども、まさに咲き乱れるといった状態だった。そして、カタクリを見つけた。夢中でシャッターを切り続けたが、このあとカタクリは、この日の終着点まで延々とルート沿いに咲いていた。まさにカタクリの山といった表現が適切だろう。カタクリに飽きてしまい、コースの終盤には見向きもしなくなった自分の身勝手さに苦笑してしまった。
ザゼンソウやエンレイソウなども、至るところで見られた。トレッキングに訪れる人も国内の山岳観光地に比べてそれほど多くはない。それに、島には野生のイノシシや鹿などが棲息していないことが幸いして、多くの山野草が残っているのだろう。もちろん群落には、盗掘防止のために金網や柵などはない。

稜線を歩くと左右とも海が見える、なんとも珍しい風景が広がっていた。そして、金北山の山頂レーダーが間近に迫ってくると、残雪のトレイルになった。ステップを切って登った。まさか佐渡島で雪の上を歩くとは思わなかった。不思議な感じだった。
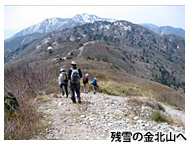 この日、このトレッキングコースで出会ったパーティは、わずかに5組だったろうか。車で登れるドンデン山(940m)あたりであれば、もう少し多かったかもしれない。ただ、私たちも含めて、トレッカーの大半が中高年だった。本来ならこのような野草の宝庫と、すばらしい自然は、子どもたちや若者たちにこそ見せておくべきだと思う。この先、中高年のトレッカーが去った後、トレイルは荒れ、やがて廃道になって訪れる人のない自然に戻るのかもしれない。これがいいのか悪いのか、やや複雑である。この傾向は、佐渡島だけでなく、国内の山々にも全てあてはまる。ただ、自然のすばらしさは歩いて、見て、感じないとわからない。
この日、このトレッキングコースで出会ったパーティは、わずかに5組だったろうか。車で登れるドンデン山(940m)あたりであれば、もう少し多かったかもしれない。ただ、私たちも含めて、トレッカーの大半が中高年だった。本来ならこのような野草の宝庫と、すばらしい自然は、子どもたちや若者たちにこそ見せておくべきだと思う。この先、中高年のトレッカーが去った後、トレイルは荒れ、やがて廃道になって訪れる人のない自然に戻るのかもしれない。これがいいのか悪いのか、やや複雑である。この傾向は、佐渡島だけでなく、国内の山々にも全てあてはまる。ただ、自然のすばらしさは歩いて、見て、感じないとわからない。もう一度訪れてみたいと思う、佐渡島だった。
参考までに、この時期だけかどうかはわからないが、稜線に出るまでブヨの大群がまとわりついてきた。防虫剤か防虫ネットがあればいいだろう。刺されたあと、数日間は痒みに悩まされた。
また、金北山からは航空自衛隊の管理道路を歩くので、事前の届出が必要だ。用紙はダウンロードし、FAXで届けることになっている。
http://www.ryotsu.sado.jp/trek/05_info/todoke.doc
(次回へつづく)
■バックナンバー
■筆者紹介
中村 達(なかむら とおる)
1949年京都生まれ。アウトドアジャーナリスト。
NPO法人自然体験活動推進協議会理事、国際アウトドア専門学校顧問、NPO法人比良比叡自然学校常務理事、日本アウトドアジャーナリスト協会代表理事、東京アウトドアズフェスティバル総合プロデューサーなど。
生活に密着したネーチャーライフを提案している。著書に「アウトドアズマーケティングの歩き方」「アウトドアビジネスへの提言」「アウトドアズがライフスタイルになる日」など。『歩く』3部作(東映ビデオ)総監修。カラコルムラットクI、II峰登山隊に参加。日本山岳会会員。