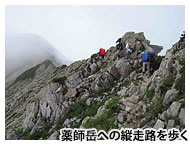- 第153回 - 著者 中村 達
『35年ぶりの北アルプスの縦走』
35年ぶりに、北アルプスの立山から薬師岳までを歩いてきた。天候にも、メンバーにも恵まれた、大変楽しい登山だった。
このコースをはじめて歩いたのは高校3年生だった。所属していた山岳部の夏山合宿で、薬師岳から剣岳までの縦走をした。担任の教師がホームルームで、「受験だというのに山に行く生徒がいる」と名指しで非難したが、何とかごまかして夏山合宿に参加した。大学の山岳部でもこのルートを歩いたが、高校時代のほうが、はるかに強烈な記憶が残っている。
 ただ、記憶といってもかなり局部的で、ここでテントを張ったとか、ここで水を補給したとか、ここで渡辺の粉末ジュースを飲んだとかはしっかり覚えているが、ルートの様子はすっかり忘れていた。いかに記憶がいい加減か思い知らされた。もっとも当時は40~50kgのキスリングを背負って、下ばかりを見て歩いていて、景色を楽しむ余裕もなかった。高山植物の名前もほとんど覚えなかった。興味がなかった。ただ、ひたすら登ることだけだったような気がする。
ただ、記憶といってもかなり局部的で、ここでテントを張ったとか、ここで水を補給したとか、ここで渡辺の粉末ジュースを飲んだとかはしっかり覚えているが、ルートの様子はすっかり忘れていた。いかに記憶がいい加減か思い知らされた。もっとも当時は40~50kgのキスリングを背負って、下ばかりを見て歩いていて、景色を楽しむ余裕もなかった。高山植物の名前もほとんど覚えなかった。興味がなかった。ただ、ひたすら登ることだけだったような気がする。学生時代と大きく変ったのは、若い人たちの姿が極めて少なかったことだ。山岳部時代は、学生や社会人山岳会の若者たちで、山は完全に占拠されていたし、10人20人といった大パーティも、決して珍しくはなかった。いまは、中高年者の元気なオバサンたちばかりが目立つ。そんな中で、北薬師岳の山頂で出会った関西外大の5人のワンゲル部員たちは、一服の清涼剤のように爽やかだった。同行者たちが一様に、「うれしいね、若い人たちが山に登るのは」と感動しきりだった。
それに山小屋で一生懸命働く若者たちの姿もとても印象的だった。ある山小屋では、たった3人の若者たちだけで、50人もの登山客の切り盛りをしていた。早朝の3時30分頃には厨房で朝食の準備をはじめていた。キャベツをリズミカルに刻む音で目が覚めた。
他の山小屋でも夜の8時30分に消灯、朝の5時には朝食という生活の中で、若者たちが一生懸命に働き、登山客の中高年者をかいがいしく世話する姿がとても印象的だった。中高年が山で遊び、若者たちが山で働く、そんな時代なのか?
下山口の折立へ向かって急坂を下っていると、中学生の一団に出会った。これから薬師岳に登りに出かけるのだそうだ。ザックの大きさからすると、ちょっときつめの日帰り登山に見えた。元気に「おはようございます」と挨拶をしてくれた。少し遅れて引率の先生だろうか、「いゃー、ついていくのが大変です!」と、汗を拭きながら子ども達の後を追いかけていった。
(次回へつづく)
■バックナンバー
■著者紹介
中村 達(なかむら とおる)
1949年京都生まれ。アウトドアプロデューサー・コンセプター。
通産省アウトドアライフデザイン研究会主査、同省アウトドアフェスタ実施検討委員などを歴任。東京アウトドアズフェスティバル総合プロデューサー。
生活に密着したネーチャーライフを提案している。著書に「アウトドアズマーケティングの歩き方」「アウトドアビジネスへの提言」「アウトドアズがライフスタイルになる日」など。『歩く』3部作(東映ビデオ)総監修。カラコルムラットクI、II峰登山隊に参加。